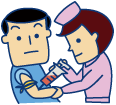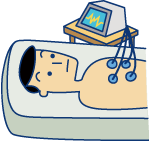健診結果の見方

健康診断の健診結果はいかがでしたか?
「再検査」など呼び出しがあった方は、必ず受診して医師の指示に従ってください。
「異常なし」の方でも、昨年、一昨年のデータとよく見比べてみてください。検査結果が基準値の範囲であっても、年々数値が悪化している場合は注意が必要です。経年変化を見るためにも、1年に1回は必ず健診を受けましょう。
特定健康診査の基本項目
保健指導判定値は、厚生労働省が制定した特定保健指導に用いる判定値です。基準値は、医療機関により数値が異なる場合がありますので、健診機関等からの結果表でご確認ください。
身体計測
| 腹囲cm | 保健指導 判定値 |
男性85以上、女性90以上 |
|---|---|---|
| 検査内容 | 内臓脂肪の蓄積を調べます | |
| わかる こと等 |
体脂肪には皮下脂肪と内臓脂肪があり、内蔵脂肪が過剰にたまると、たとえ体重が適正であっても、糖尿病や心筋梗塞、脳卒中などを引き起こしやすくなります。
|
|
| BMI 体格指数 |
保健指導 判定値 |
25.0以上 |
| 検査内容 | 身長と体重から「肥満」や「やせ」でないかを調べます | |
| わかる こと等 |
BMI(体格指数)=体重(㎏)÷身長(m)÷身長(m)の式で算出します。
|
血圧
| 血圧 mmHg |
保健指導 判定値 |
収縮期 130以上 拡張期 85以上 |
|---|---|---|
| 検査内容 | 血管にかかる圧力を調べます | |
| わかる こと等 |
心臓から全身に血液を送り出す際に、血管の中に加わる圧力が血圧です。血圧は心臓が縮んで血液を送りだすときの収縮期血圧と心臓が元の大きさに戻ったときの拡張期血圧があります。
|
血中脂質検査
| 中性脂肪 ㎎/dl |
保健指導 判定値 |
150以上 |
|---|---|---|
| 検査内容 | 血液中に含まれる脂質の量から動脈硬化の危険度などを調べます | |
| わかる こと等 |
脂質や炭水化物などを多く含む高カロリーの食品をとりすぎると増加します。中性脂肪が多くなるとLDLコレステロールが増え、また血栓ができやすくなり、動脈硬化を促進します。
|
|
| HDL コレステロール ㎎/dl |
保健指導 判定値 |
39以下 |
| 検査内容 | 血液中に含まれる脂質の量から動脈硬化の危険度などを調べます | |
| わかる こと等 |
善玉コレステロールと呼ばれ、血管壁にこびりついたコレステロールを取り除き、動脈硬化を防ぎます。 | |
| LDL コレステロール ㎎/dl |
保健指導 判定値 |
判定は健診機関ごとに異なる場合がありますので健診の結果表でご確認ください。 |
| 検査内容 | 血液中に含まれる脂質の量から動脈硬化の危険度などを調べます | |
| わかる こと等 |
悪玉コレステロールと呼ばれ、血管壁にこびりついて動脈硬化を促進します。LDLコレステロールが増えるほど狭心症、心筋梗塞、脳卒中の発生率が高くなります。
|
肝機能検査
| GOT (AST) IU/l ・ GPT (ALT) IU/l |
保健指導 判定値 |
判定は健診機関ごとに異なる場合がありますので健診の結果表でご確認ください。 |
|---|---|---|
| 検査内容 | 血液を採取して肝臓の機能を調べます | |
| わかる こと等 |
2つとも肝臓に含まれる酵素で、ともに肝臓が原因の場合がほとんどです。
|
|
| γ-GTP IU/l |
保健指導 判定値 |
判定は健診機関ごとに異なる場合がありますので健診の結果表でご確認ください。 |
| 検査内容 | 血液を採取して肝臓の機能を調べます | |
| わかる こと等 |
GOTやGPTに似ていますが、飲酒量と強く連動するのが特徴です。飲み過ぎの注意信号ですので、高かった方はお酒の量を減らしましょう。晩酌は1日1合までとし、週1日以上は飲まない日を作ってください。飲み続ければGOTやGPTが上昇し、肝炎が待っています。 |
血糖検査
| 空腹時 血糖 mg/dl |
保健指導 判定値 |
100以上 |
|---|---|---|
| 検査内容 | 血液を採取して糖尿病の危険度を調べます | |
| わかる こと等 |
ブドウ糖をエネルギー源として利用する時に必要なのが、すい臓から分泌されるインスリンというホルモンです。インスリンの働きが悪いと血液中のブドウ糖が十分利用されず、血液中にブドウ糖(血糖)が増えます。
|
|
| ヘモグロビンA1c % |
保健指導 判定値 |
5.6以上(NGSP) 5.2以上(JDS) |
| 検査内容 | 血液を採取して糖尿病の危険度を調べます | |
| わかる こと等 |
血中でブドウ糖と結合したヘモグロビンの割合をみることで、過去1~2ヵ月の血糖値がわかる検査方法です。
|
尿検査
| 尿糖 | 保健指導 判定値 |
陰性(-) |
|---|---|---|
| 検査内容 | 尿中の糖の量から糖尿病の危険度を調べます | |
| わかる こと等 |
高血糖の状態だと尿にも糖がでます。 | |
| 尿蛋白 | 保健指導 判定値 |
陰性(-) |
| 検査内容 | 尿を採取して腎臓の機能を調べます | |
| わかる こと等 |
 通常は尿に検出されない蛋白が陽性の場合は、腎臓病や高血圧、糖尿病などが原因のことがありますので、強い蛋白尿があれば必ず医師受診を。軽度なら何でもない場合も多いですが、足のむくみ(浮腫)や血圧の上昇があれば、医師の診察が必要です。 通常は尿に検出されない蛋白が陽性の場合は、腎臓病や高血圧、糖尿病などが原因のことがありますので、強い蛋白尿があれば必ず医師受診を。軽度なら何でもない場合も多いですが、足のむくみ(浮腫)や血圧の上昇があれば、医師の診察が必要です。
|
特定健康診査の詳細項目
貧血検査
| 赤血球数 万/mm3 |
保健指導 判定値 |
判定は健診機関ごとに異なる場合がありますので健診の結果表でご確認ください。 |
|---|---|---|
| 検査内容 | 血液を採取して貧血の有無を調べます | |
| わかる こと等 |
【貧血といわれたら】
|
|
| ヘモグロビン (血色素) g/dl |
保健指導 判定値 |
判定は健診機関ごとに異なる場合がありますので健診の結果表でご確認ください。 |
| 検査内容 | 血液を採取して貧血の有無を調べます | |
| わかる こと等 |
【貧血といわれたら】
|
|
| ヘマトクリット % |
保健指導 判定値 |
判定は健診機関ごとに異なる場合がありますので健診の結果表でご確認ください。 |
| 検査内容 | 血液を採取して貧血の有無を調べます | |
| わかる こと等 |
【貧血といわれたら】
|
心電図検査
| 心電図 検査 |
|
|---|---|
| 検査内容 | 心臓の機能を調べます |
| わかる こと等 |
心電図異常には不整脈や虚血性変化(狭心症などの傾向)などが含まれます。強い異常があれば必ず医師受診を。軽い異常であっても、動悸、息切れ、運動時の胸痛、胸の締め付け感などがあれば、医師の診察を受けてください。
|
眼底検査
| 眼底 検査 |
|
|---|---|
| 検査内容 | 目の奥の網膜の状態から動脈硬化の程度を調べます |
| わかる こと等 |
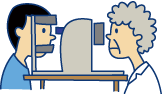 眼底検査では、網膜の出血や動脈硬化、高血圧影響などを調べています。出血など、はっきりした異常がある場合は眼科受診が必要です。軽い異常があった方は、血圧を正常に保つことに特に注意してください。禁煙や糖尿病の予防も大切です。 眼底検査では、網膜の出血や動脈硬化、高血圧影響などを調べています。出血など、はっきりした異常がある場合は眼科受診が必要です。軽い異常があった方は、血圧を正常に保つことに特に注意してください。禁煙や糖尿病の予防も大切です。
|
40歳以上の方は・・・
健診の結果から必要な方には特定保健指導のご案内が届きます。特定保健指導とは、専門スタッフがあたなの健康管理をサポートするものです。ご自身の健康管理のためにご利用ください。
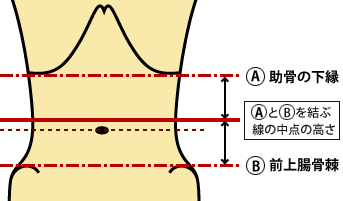 へその位置が下に移動しているときは、(A)助骨の下縁と(B)前上腸骨棘の中点の高さで測定します。
へその位置が下に移動しているときは、(A)助骨の下縁と(B)前上腸骨棘の中点の高さで測定します。 日本肥満学会が設定した肥満症の診断基準では、BMI18.5未満が低体重、25以上が肥満です。25を超えると高血圧、糖尿病、高脂血症が発症しやすく、心臓病や脳卒中につながります。
日本肥満学会が設定した肥満症の診断基準では、BMI18.5未満が低体重、25以上が肥満です。25を超えると高血圧、糖尿病、高脂血症が発症しやすく、心臓病や脳卒中につながります。
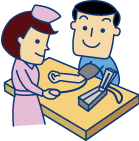 高血圧は、脳卒中、心臓病の最大の原因となりますので、血圧が高かった方は、定期的な測定が必要です。特に160/100以上あった方は、薬による治療も必要となります。
高血圧は、脳卒中、心臓病の最大の原因となりますので、血圧が高かった方は、定期的な測定が必要です。特に160/100以上あった方は、薬による治療も必要となります。