反転攻勢、日本の少子化
「時局講演会」を開催

伊佐進一
厚生労働副大臣
健保連大阪連合会は9月6日の理事会終了後、引き続いて「時局講演会」を開催した。「反転攻勢、日本の少子化~少子化の今日的課題と保険者に求めること~」をテーマに、伊佐進一厚生労働副大臣(当時)が講演。
少子化問題は、多くの先進国が悩んできた。どんどん出生率が低下していくなか、多くのヨーロッパ諸国は1980年代に入って少子化対策を始めた。すると、出生率の低下が止まり、上向いたところもあった。
そこで頑張れなかったのが日本、ドイツ、韓国。しかし、ドイツは2000年代に入って本気で少子化対策を始め、出生率低下を止めた。最後まで頑張り切れなかったのが日本と韓国である。
今の日本の出生率は1.2程度。40年後には人口が3分の2になると言われている。少子化対策とはある意味、少母化対策とも言われ、減少する母親を少子化対策で増加させ、その増加した母親が子を産む。つまり、2世代というかなりの時間がかかる。そのため、今が最後のチャンスという思いで取り組まなければならない。
少子化対策

①児童手当の拡充
支給対象を高校生まで引き上げる。さらに第3子以降は一律で月3万円に引き上げる。所得制限も撤廃し、親の所得に関係なくすべての子を対象に支給することとなる。
②育児休業給付金の引き上げ
現在、所得の約7割が給付されているが、これを最大8割(社会保険料がかからないため、実質は育休前の手取り賃金と同程度の金額)となるように検討している。
③出産育児一時金の引き上げ
今年の4月から、42万円(産科医療補償制度を含む)から、50万円に引き上げられた。
前述の①~③など、色々な施策を行うのだが、皆さんの一番の関心は財源をどうするかという話だと思う。全部で3.5兆円である。
少子化対策の財源
岸田総理大臣の「増税しない・保険料の新たな負担も考えていない」との発言により、税でもなく保険料でもなければ何になるのか。官邸の判断では、徹底的な歳出改革、つまり、社会保障のなかで医療や介護を削っていくということとなる。年末に向けて財務省との交渉で、どのように歳出改革を行うかという大きな議論となる。
もう一つは、支援金制度(仮)と言われるもの。未来戦略には「支援金制度による負担が全体として追加負担とならないよう目指す」と示されている。これは、歳出改革を行うと医療や介護全体の総額が減り、保険料負担も減る。その減った分をこども子育て支援に入れるというメカニズムである。
医療DXの重要性
経済成長によりGDPを上げることも考えなければならない。日本の得意分野である医療や介護に投資しなければならないとの思いで、副大臣になって一生懸命進めているのが医療DXである。
国民皆保険制度で、国民一人ひとりのデータがある。これらバラバラのデータをプラットフォーム化し、疾病予防や介護予防、研究開発、創薬などにつなげられないか。データ整備により、国民一人ひとりの健康に役立たせていくことが日本にできれば、世界に打っていける色々なものができると思っている。
大阪自動車販売店健保組合 植田 勝 常務理事が質問
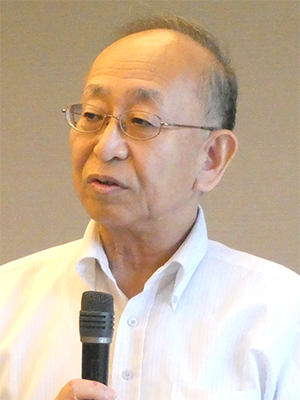
植田勝
常務理事
伊佐副大臣に対して、会場の大阪自動車販売店健保の植田勝常務理事から、「少子化対策は出生率向上のため出産支援を拡大し、安心して子育てができる環境づくりをすることだと思うが、予算関連ばかりが話題になっている。安心して出産・育児ができる労働・社会環境の整備も検討すべきと考えるがいかがか」「負担の新たな枠組みとして2026年度から支援金制度が想定されている。医療保険とは別建てで検討されると思うが、支援金という名称は後期高齢者支援金をイメージし、今後、制度設計を変えないか不安になる。できれば名称の再検討をお願いしたい。あわせて、少子化対策推進に当たり、健保組合の深刻な財政状況にご配慮いただき、財政支援等適切な財源の検討をお願いしたい」の2点について質問と要望。
伊佐副大臣は、前者について「例えば出産育児一時金について。50万円に引き上げたが、その分、出産費用が便乗値上げされると意味がないため、現在調査中である。また、出産費用の見える化についても着手している。また、出産・育児における行政との連携や、保育の現場に対する制度設計も考えている」。後者については「支援金という名称については、皆さんの心象風景も受け止め、今後、議論をしていきたい。財政支援についてももっともだと思う。これまでの交付金等に加えて上乗せを決定している。財政当局とも議論をしながら、できる限り現役世代にも寄り添えるような形で頑張ってまいりたい」とそれぞれ回答した。
健保連 河本専務理事あいさつ

河本滋史
健保連専務理事
少子化対策は絶対に必要な国の課題であると認識しており、国の少子化対策についても賛成の立場である。ただ、その財源の負担については、現役世代だけに負わせるのではなく、高齢者も含めて幅広く全世代で分担していきたい。また、年末に向けた支援金制度に関しては、医療保険制度とは別建てで制度を考えていただきたい。
さらに、こども子育て支援で現役世代の負担が増えても、他の制度等含めたトータルでは現役世代の負担が決して増えないよう、全世代型社会保障負担構造改革を継続して進めていただきたい。
本日のお話でも、その辺りをしっかり踏まえていただけると思っている。引き続きよろしくお願いしたい。


