健康セミナー(オンデマンド配信)
10月11日~10月25日、健康セミナーについてオンデマンドにて講演動画を配信。関西医科大学 健康科学科 教授/同附属病院健康科学センター長 木村穣氏が「コロナ時代の新しい生活習慣病予防」をテーマに講演されました。
(以下に講演要旨)
コロナ時代の新しい生活習慣病予防
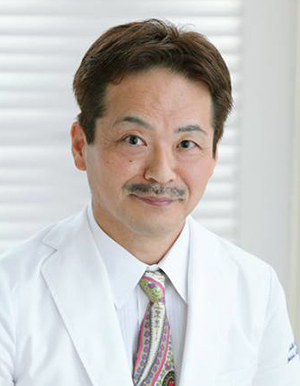
木村 穣 氏
コロナ禍での活動自粛で、在宅勤務が増え、休日の旅行や運動などの機会も減り、多くの人の活動量は減っています。この活動量の低下による肥満、糖尿病や高血圧などの生活習慣病の発症、悪化は、コロナ禍の健康二次被害として大きな問題となっています。私の所属する関西医科大学健康科学センターでも毎年体力テストとして運動時の酸素摂取量などを評価していますが、コロナ禍ではこれまでになかった体力の低下が目立っています。特に歩く以上のやや強い運動強度での体力の低下が目立っています。日常での最低限の活動は保たれているのですが、少し強い運動レベルの体力が低下しているということです。
この体力の低下に影響する一つの原因が筋肉です。筋肉は使わないと減っていきます。コロナ禍では歩く以上の強さの運動が減ってくるので、筋力も低下してきます。特に高齢者ではその影響が強く出ています。ではこの筋肉の低下はどこまで健康に影響してくるのでしょうか。
これまで、不活動により体の脂肪が増え、その脂肪の蓄積で肥満になり、動脈硬化につながるとされてきました。もちろんこの考えは正しいのですが、一方で痩せている人も、動脈硬化が強く、結局長生きにつながっていません。この痩せが健康に悪い理由は筋肉が少ないということです。ではなぜ筋肉が少ないと長生きできないのでしょうか?
その答えは筋肉の隠れた働きにありました。すなわち筋肉も脂肪や他の内臓と同様に様々なホルモン(活性物質)を分泌し、動脈硬化予防や脂肪燃焼に役立っていたのです。さらに最近の研究では、脳神経細胞にも働き、脳機能を活性化させていることもわかってきました。すなわち筋肉低下は、転倒や骨折などの危険だけではなく、動脈硬化や認知症などにも大きく関わっていることが分かってきました。この筋肉の低下した状態をサルコペニアと称し、特に高齢者では大きな問題となっています。ということで、コロナ禍の不活動は、体力だけではなく筋肉にも十分に気をつけていく必要があります。
筋肉で気をつける点は、筋トレとして筋肉運動のみを行うと、かえって筋肉が少なくなることがあります。なぜなら筋肉は刺激によって増えますが、その効果はあくまでも原料となるタンパク質が十分に体内にある場合に限られます。メタボ(肥満)を気にして、食べないで筋トレすると筋肉は消耗してかえって減っていきます。これは最悪の結果です。ぜひ筋トレをする場合には、タンパク質の摂取を心がけてください。少し気をつけてタンパク質摂取を心がければ、通常の食事でもタンパク質は十分摂取可能です。ぜひバランスのよい食事を心がけてください。
さらに栄養は免疫機能にも影響します。コロナウイルスに負けないためにもしっかり栄養を取って、運動も行ってください。
コロナ禍での皆様のご健康を心よりお祈り申しあげます。


