 |
 |
天高く馬肥ゆる秋が過ぎ去ろうとしているが、新型コロナウイルス禍は一向に収まらない。この状況を非常ではなく日常と認識し、長期的に付き合っていく覚悟をしなくてはならない。
新型コロナは我々健保財政にも大きな影響を及ぼした。令和2年度当初予算時に比べ、平均標準報酬月額は4.0%減、平均標準賞与額は12.9%減となった。これらにより、保険料収入額が約4000億円規模の減少となり、実質保険料率は当初予算時の9.58%から10.08%と0.5ポイント上昇する見込みだ。
その反面、4月と5月の医療費は対前年同期比で大幅なマイナスとなり、その結果、保険給付費も大きく減少した。一時的ながら健保財政面で一息つくことができた健保組合もあるのではないだろうか。
しかし、1日当たりの医療費は入院外・調剤で増加している。不要不急でなく、本当に必要な治療を受けた方が多かったのではないか、と想像される。しかも6月以降、このマイナス幅は減少している。早晩、保険給付費は対前年同期比増といういつもの傾向に戻ってしまうだろう。あるいは、治療を控えたことで病状が悪化し、さらに増加することすら懸念される。
医師会は常々「早期に診断し、早期治療することが医療の鉄則だ」として、受診抑制につながる施策にはどちらかというと否定的だ。しかしながら、すべての医療行為がそうだと言えるだろうか。今回の新型コロナによる受診抑制と、その後の動向は格好の検証材料になるだろう。健保連は「受診控えの分析は重要であり、健保連としても新型コロナによる患者の受療行動、意識の変化に関する調査を検討している」としてきた。受診控えによる今後の悪影響がどれだけ出てくるのかも検証したいところだ。
日本の医療費は昨年度、前年から1兆円増加し、2022年を境にさらに加速していく見込みだ。その増加のカーブを少しでも緩やかにしていかなければならない。我々健保組合は、各種保健事業や医療費適正化に取り組んでいる。その一環で「経済性も考慮した医薬品の処方の推進」なども訴えてきた。昨年9月には、「花粉症治療薬のスイッチOTC医薬品の流通状況や、医療の必要性に応じた保険償還率を段階的に設定している海外の制度等を参考に、OTC類似薬全般について、保険適用からの除外や自己負担率の引き上げを進めるべきである」という提言を行った。
健保組合の財政は、これまで以上に厳しい状況が続くだろう。まずは保険者として、加入者に対し、正しい医療機関への受診行動などを周知し、効率的な医療資源の活用に向けた取り組みを進める必要がある。また、健康づくりや重症化予防などにも取り組み、現在の医療保険制度を持続可能なものにしなければならない。
その上で、まだ検討の余地はあるだろう。新型コロナや2022年危機という問題を抱えている今だからこそ、高齢化・高度医療化等への対策として、今までになかったような大胆な制度設計の改革や、大きな変化をもたらす発案を期待せずにはいられない。 |
| |
(H・K) |
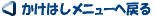 |
 |
|
 |