 |
| 健保連大阪連合会は10月3日、大阪市北区の大阪工業大学梅田キャンパス「常翔ホール」で「健保組合存続のため 今何が必要か? あしたの健保組合を考える大会 PART5」を開いた。大会には160人の健保組合関係者などが出席。近畿地区各府県からも多数の参加があった。大会では前半に「全世代型社会保障の光と影」をテーマに、大林尚(つかさ)氏(日本経済新聞社 上級論説委員)が講演。後半には「健保組合存続のため 今何が必要か?」をテーマに、長尾敬衆議院議員、伊佐進一衆議院議員らによるシンポジウムが行われた。 |
 |
 |
 |
 |
| 森脇紳二大阪連合会副会長 |
健保連は、高齢者医療の負担構造改革や実効ある医療費適正化対策の強化など、要求実現活動を全国で展開している。大阪連合会による「あしたの健保組合を考える大会」は、その一環として今回で5回目の催し。当初は4月に開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により延期となり、今般の開催となった。
大会には、大阪府内の健保組合役職員をはじめ、府外の近畿地区各府県の健保組合からも多数参加があり、160人が集まった。
主催者を代表し、大阪連合会・森脇紳二副会長が開会のあいさつを行った。森脇副会長は「新型コロナウイルスによる健保組合における財政影響は、リーマンショック時と同等、あるいは、それを超えた保険料収入低下の影響が長期化する傾向にあり、来年度以降もさらに厳しい状況が予測される。このような状況下であっても2022年危機は迫っており、コロナ禍によりその時期が早まるのではないかと危機感を覚えている。健保組合は限られた財源のなかで、本来の保険者機能を発揮し、事業所とのコラボヘルスなどの保健事業や医療費適正化に取り組んでいる。国民皆保険の中核を担う健保組合の財政安定化を図り、国民皆保険制度を維持・発展させなければならない。そのためには、給付と負担のバランス、後期高齢者の窓口負担原則2割導入など、高齢者医療の負担構造改革の早期実現を粘り強く訴えていかなければならない。この大会を通じ、皆さんの意思結集を図り、健保連本部と連携のうえ、今後の取り組みを強化していくことをお願いする」と述べた。
大会前半には大林尚上級論説委員(日本経済新聞社)が「全世代型社会保障の光と影」をテーマに講演。後半では、長尾敬衆議院議員(自民党・大阪14区)、伊佐進一衆議院議員(公明党・大阪6区)、健保連の河本滋史常務理事と大林氏によるシンポジウムが行われた。
 |
| 大林尚上級論説委員 |
基調講演「全世代型社会保障の光と影」(内容抜粋)
大林上級論説委員
新型コロナの影響により、2020年度の歳出は2度の補正を経て160兆円規模であり、新規国債発行90兆円、この結果、基礎的財政収支の赤字は66兆円となった。財政支出の拡大が進められたが、この膨大な債務を、誰が、いつ、どうやって返すのかという議論が欠けていることは問題である。
財政再建目標について、政権は18年の骨太方針で25年に先送りしたが、今年の骨太方針では目標時期の明示さえ見送った。その後、内閣府は、黒字転換は早くて29年度という試算を出したが、29年度に黒字転換するためには、名目3%以上、実質2%超という日本の経済の実力からみて現実離れした成長率が前提というものである。おそらく29年度も難しいということが見えてくるため、財政改革のゴールを定める意志があるのか疑いたくなる。ゴールがなければ、我々はゴールしようとすら思わなくなるリスクがあることを私は心配している。
社会保障制度の財源は、主に保険料と税金だが、国民負担率について、平成の30年間において租税負担率はほとんど変わらず、保険料負担が増加している。この公費負担を上げられないところが今の政治の大きな課題であり、このツケは結局、財政赤字に依存していることになる。政治家にとって、保険料は取りやすく、税は取りにくいという特性があり、消費税率の引き上げについては、非常に慎重になっていた。
 |
| 河本滋史健保連常務理事 |
昨年12月の全世代型社会保障検討会議において、後期高齢者の窓口負担を1割から2割に引き上げるかどうかが一番のポイントだった。この中間報告を受けて、新聞各紙においては、それぞれの社論の考え方があるとはいえ、お茶を濁したような表現もみられた。この問題は喫緊の課題であるため、この10月に再開される会議の議論を注目しており、年末の最終報告における原則2割負担にするということをぜひ求めたいと思っている。
シンポジウム「健保組合存続のため 今何が必要か?」
まず、シンポジウムのコーディネーターである健保連の河本滋史常務理事から、直近の状況を踏まえた健保連の主張について説明があった。それらを踏まえ、長尾敬衆議院議員、伊佐進一衆議院議員、大林尚上級論説委員をパネラーとして進められた。
【給付と負担の見直し】
伊佐議員は「おそらく多くの与党の政治家は、後期高齢者の自己負担割合について、低所得者等を除き、2割にもっていかなければいけないと思っていると思う。あとは、原則と例外の線引きをどこにするかを議論しなければならない」と述べた。大林氏からは「ポイントは、やはり年末の全世代型社会保障検討会議の最終報告で、2割負担の対象がどこまで認められるかということ。私見として、マイナンバー機能を強化することで、年齢ではなく所得・資産によって負担割合を決めていくことが理想ではないかと思っている」との意見があった。
 |
| 長尾敬衆議院議員 |
【コロナ禍における健保組合への財政支援】
長尾議員は「すでに後期高齢者支援金等の拠出金負担で苦しんでいる健保組合に対して、引き続き財政支援は必要であると思うが、その内容は十分ではなかった。健保組合が解散して協会けんぽへ移行すれば、国の負担は増加し、また保険料にも影響がでる。このままでは、国民皆保険制度が崩壊するかもしれないため、やはり給付と負担の問題などは先送りできない。今は有事であるため、プライマリーバランスとは別枠で財政支援を行う必要があると思う」と述べた。
【これからの社会保障改革の見通し】
大林氏は「社会保障改革とは、日本の人口構造のこれからの大きな劇的な変化を考えると、終わりのない改革だと思う。これまでも、現役世代の自己負担割合の引き上げや、消費税率の引き上げなど、その時々の政権が行ってきた取り組みはあるが、給付に関する改革はあまり見当たらない。選挙が絡むと負担・給付の改革は表に出しにくいという問題は理解しているが、これからの選挙ではしっかりと体制を整えて、改革に取り掛かってほしい」とし、さらに「健保組合は財政的に豊かであると思われているところがあるが、高齢者医療に対して収入の5割近い負担をしている。これを当然だと思われているところがあるが、本来、高齢者の病気やけがの治療というのは、保険原理が働きにくい特性があると思う。そういった方々への給付は、税財源、公費を手厚く投入するのが理想的だと考える。税財源の確保はなかなか進まないという現実はあるが、欧州の状況を踏まえると、日本の消費税率が10%のままというのは考えにくく、ぜひ菅政権にはもう一度、社会保障と税の一体改革に取り組んでいただきたいと考えている」と述べた。これにあわせて伊佐議員は「これからは具体的なメニューを示していくことになる。どういう給付にはどれぐらいの財源が必要で、そのための負担はどうなるのかということを説明し、国民に選んでもらうということが大事ではないかと思っている」とした。長尾議員は「給付と負担の話も大事だが、健康増進と重症化予防策も重要である。人生100年時代、病気にかかりながら歳を重ねるのか、健康で過ごすのでは人生の意味合いもがらりと変わり、医療費に対する影響も違ってくる。極論では、人生で一度も入院などなく、医療機関にもかからないような人生100年時代を、医療制度の問題点を通して考えていくことが非常に重要ではないか」と述べた。
 |
| 伊佐進一衆議院議員 |
【今後の医療費の適正化】
伊佐議員は「薬価に対する議論は必要。患者にとって、高額であっても必ず必要であれば保険収載すべきである。市場規模を踏まえて改革のルールを決めて、国民に示すことができれば、患者にとっても安心感をもったなかで薬価改革が進められるのではないか。また、心疾患や脳血管疾患についても、政治がカバーしていくべきでないかと思っている」と述べた。長尾議員は「健康増進や重症化予防にもっと取り組むことで適正化につながると思っている。ただやみくもに予算を削るという概念ではなく、医療のお世話になる可能性をできるだけ低くもっていくという適正化の方法も、これからの時代、皆さんと一緒に考えていくことができればと思う」と述べた。
【健保組合の今後】
伊佐議員は「自動的に収入の5割近くが高齢者医療にとられている状況は何とかしないといけない。各都道府県の保険者協議会において、他の保険者と議論を進めることが大事」と述べた。長尾議員は「1にも2にも健康増進、重症化予防の保険者機能を発揮していただきたい」とした。大林上級論説委員は「政治力や資金力ではどうしても劣る支払い側としては、戦略で戦うことが重要。国民皆保険を守る国会議員連盟の発足もあり、ぜひ、存在感のある健保組合・健保連になっていただきたい」と述べた。
会場から要請
 |
| 大林尚上級論説委員 |
シンポジウム出席者に対して、会場参加者である大阪薬業健保の青島和宏専務理事から、次の2点について要望と質問があった。①高齢者医療制度への過重な拠出金負担に追い打ちをかけるような新型コロナウイルス感染症の拡大による財政影響。加入事業所の賃金や賞与の減少、保険料の納付猶予や標準報酬月額の特例改定などにより、保険料収入は大幅に減少することは確実で、来年度の予算編成もままならない状況にある。この終わりの見えないコロナ禍において、健保組合の急激な財政悪化を防ぐため、早急に国家的な支援策を講じていただきたい。②社会保障制度の財源について。昨年10月に実施された消費税率引き上げに伴う増収分は、本来の目的であった年金・医療・介護の社会保障分野ではなく、ほとんどが基礎的財政収支の黒字化や教育の無償化などに充てられた。今回のコロナウイルス感染拡大により、来年度、健保組合は非常に深刻な状況になる。今後の社会保障制度を維持・存続させるため、税と社会保障の改革の第2弾として、消費税率の引き上げなど、現行の税制度の根本的な見直しなどについてお聞きしたい。
まず①について、長尾議員は「恒常的な財政悪化とコロナによるものとは、それぞれ違うフィールドで議論する必要がある。しかし、まずは目の前にあるコロナによる財政悪化を解決しつつ、次の段階に進むという2段階方式で年末の税制改正議論を迎える。健保組合からも厳しく議員を突き上げていただきたい」とした。伊佐議員は「従来の交付金等への上乗せがあるかどうかが今後の肝となる。しかし、財務省と日頃からコミュニケーションをとっているが、コロナによる減収に対する補填は行わないようだ。つまり、健保組合としては、コロナがあるから健診等ができなくなって大変なのだ、といったような武器を我々にいただければありがたいと思う」と述べた。
 |
| 青島和宏専務理事 |
続いて②について、大林氏は「巨額になったコロナ対策費はやむを得ない支出だったと思う。しかし、一般財源の範囲内で行ったため、本来の予算と一緒になってしまったところは残念だった。例えば、コロナ対策特別会計のようなものを作り、財源を手当てしたうえで、この特別会計を何年計画で処理するのかを含めて一緒に決めればよかったのかなと思う。また、健康保険・介護保険・厚生年金を含めた社会保障三財源の保険料率が、間もなく労使あわせて30%になることは、負担の限界だと私は思う。したがって、消費税財源をどのように増やしていくのかということが、中・長期的には大きな政治課題になると思う。政府は消費増税を10年は行わないとしたが、すでに債務残高はGDPの2.5倍近くにまで積み上がっており、いずれ市場が耐えきれない状態になるかもしれないことは忘れてはいけない。これらを頭に入れ、ポスト社会保障・税の一体改革ということに、ぜひ現政権で取り組んでほしいし、与党の先生方もサポートするような取り組みをお願いしたい」とした。 |
 |
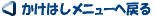 |
 |
|
 |