 |
 |
ときは3月、桜前線も北上し、花粉の飛散が全国を覆っています。
通常国会の会期も中盤を迎え、全世代型社会保障制度に対する議論の行方も気にかかりますが、健保組合では次年度の予算編成を審議する組合会が終わり、特定健診・特定保健指導などの保健事業を推進する取り組みにも力を注がなければなりません。
もちろん健保連で主張する2022年危機を乗り切るための「医療保険制度改革」諸施策について事業主・組合員への理解を深めることも重要な課題です。
偶然にも2022年は健康保険法が制定されてから100年にあたります。健康保険法は被用者を対象とする初めての医療保険制度です。その後、1958年に国民健康保険法が制定され、1961年度に国民皆保険制度が確立し、現在に至りその歴史は60年近くです。
健康保険法における基本的理念は1997年に規定された第二条に掲げられています。一部改正を経て現在は「医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない」とあります。
社会保障の医療分野でおよそ3千万人の加入者を有する健保組合は、この国民皆保険制度を支えるリーダーとして、現状に鑑みた改革をすることが責務とされています。
まさに、健保連の主張する「迫る2022年危機! 今こそ改革断行を」推進し皆保険のリーダーとして「現役世代を守りたい! 国民皆保険をささえるため」の取り組みを進めていかなければならないのです。
令和元年のこのスローガンは過去のものに比べ、一歩踏み込んだ感があります。改革断行の内容では、後期高齢者の原則2割負担、現役並み所得の後期高齢者に公費投入、保険給付範囲の見直しを重点項目とし、特に市販品類似薬を保険給付から外すなどの主張は国民目線から考えて、その理解を得ることが重要な課題だと思えます。
一方、誤解を恐れずに言えば、扇動的な部分があります。2022年に危機的な財政状況を招き、団塊の世代全員が後期高齢者になる2025年より3年も前に、国民皆保険制度が崩壊してしまうと聞こえてしまうことです。
人口構成を見ればこの世代が高齢者医療へ及ぼす影響は看過できません。75歳になれば医療費負担が1割となるだけでも現役世代の負担が増加することは明白です。その対策としての2割負担を“団塊の世代”にどのように説明するのか。
ここで団塊の世代に“現役世代を守りたい”思いを巡らせてもらうことが必要です。現役世代は、我々の子弟であり、その子供たちであること。身を切り血を流すのではなく、この血を受け継ぐために“今こそ改革断行”が必要であることを理解していただきたいと思います。
次の100年に向け、健保組合は国民皆保険制度を守るための闘いを続ける必要があります。 |
| |
(S・T) |
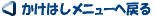 |
 |
|
 |