 |
 |
国民皆保険制度はすばらしいといわれる。国民一人ひとりにとってはそのとおりだろう。しかし、財政状態の厳しい健保組合は、まず存続できるか否かが大問題だ。存続して加入者のために独自の取り組みを展開するのか、解散して協会けんぽに移るのか。国民皆保険制度へのかかわり方には、財政状態いかんでとても大きな違いが生じることになる。
健保連の4月22日の発表によれば、保険料率10%以上の組合は2019年度予算では302組合(22%)であるが、2022年度には601組合(43%)に倍増するという。翌日の日本経済新聞は、保険料率10%以上の健保組合を「解散予備軍」としていた。
健保組合は、赤字に陥れば準備金・積立金を取り崩す。赤字が恒常的ならば、財産を減らし続ける。そして赤字が恒常的でその規模が過大ならば財政破綻、解散に追い込まれる。保険料率が協会けんぽの水準以上か否かは単なる目安に過ぎないが、赤字の場合、存続するにはそれが恒常的ではないことが重要だ。
赤字の対策は、その規模、保険料率引き上げによる保険料収入の増加額、医療費の動向、高齢者医療拠出金の動向、準備金・積立金の水準等、様々な事柄を勘案し、立案・実行する。ただし、高齢者医療の拠出金が過度に重い健保組合では、赤字対策で直ちに捻出できる額は、拠出金が主因の赤字額よりもはるかに少ない。注意すべきは、対策の効果が現れる時期および財政状態の改善への影響度だ。遠い将来に初めて十分な効果が出る対策は、現在、困窮している健保組合の財政状態の改善に有効であるとは言い難い。拠出金の重い負担が軽減されるか否かが肝心だ。
一方、十年後、二十年後の社会保障制度を見据えた取り組みを今進めることの重要性は言うまでもない。健保組合は現在、たとえ財政状態が困窮し、存続の確たる見通しが立たないとしても、国民連帯の理念を理解し、社会の一員として、将来のあるべき社会保障制度につなげる取り組みに努力している。
前出の発表では、義務的経費に占める拠出金の割合は、2019年度予算では健保組合平均で45%、同割合が50%以上の健保組合は238組合(17%)。これが2025年には50%を超え、50%以上の組合は847組合(61%)になるという。義務は果たすが存続が危ぶまれる健保組合が増加する極めて深刻な状況であるにもかかわらず、政府の対策は一時しのぎと言わざるを得ない。
消費税率の引き上げおよび社会保障の充実により、2025年を念頭に進められてきた社会保障・税一体改革は一区切りを迎えると言われている。しかし、現時点で国民皆保険制度の将来は未だ不安なままである。財政窮乏で解散の危機に瀕する組合にとって、高齢者医療の拠出金を減らせるかどうかは死活問題だ。
将来の見通しが明らかにならないなか、保険料率の引き上げは被保険者、事業主、労働組合の理解を得ることが難しくなりつつある。我々は統一地方選挙、国政選挙後の政治、行政の動きを注視し、健保連の要求の実現を一層強く求めるとともに、国民皆保険制度が危機的状況にあることの理解を促す取り組みを強力に推進する必要がある。 |
| |
(H・I) |
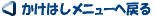 |
 |
|
 |