 |
新たな時代の健康保険組合について
― 医療費適正化と高齢者医療制度の負担構造改革 ― |
令和が祝賀ムードのなかでスタートして一月余り経過したが、新たな時代の健康保険組合について考えてみた。
健保組合のおかれている現状を見ると、急速な少子高齢化と医療費の増大により、持続可能性を問われるような危機的な状況に陥っている。令和は「明日への希望とともに、日本人一人ひとりが大きく花を咲かせる」という願いを込めて命名されたようだが、それとは違い厳しい将来が待ち受けているように見える。
ご存知のように、世界一の長寿国となった日本は、少子化も相まって、超高齢社会に突入している。今のところ、出生率の大幅な上昇は期待できそうになく、平均寿命も引き続き伸びて高齢化が進むと見込まれる。高齢化の進展と医療技術の高度化を背景として、国民医療費は増大し、2017年には42兆円に達し、今後も増加し続けていくとみられる。
政府は高齢者の医療費の抑制を目指して種々の制度改正に取り組んだが、今のところ目立った効果を上げるには至っていない。逆に、健保組合では、高齢者医療制度への拠出金の負担が重くのしかかり、これ以上耐えきれない状況に陥っている。
健保組合にとって、令和の時代は、平成から持ち越した課題である、医療費の適正化と高齢者医療費の負担構造改革を実現することが、「大きく花を咲かせる」ことになるように思える。
まず、医療費適正化に関しては、各健保組合において、特定健診・特定保健指導やデータヘルス計画への取り組みの形で着実に進んでいるが、まだまだ改善の余地はあると思われる。また、各組合独自の取り組みとともに、組合間の協力や、母体企業とのコラボヘルスも今以上に進める必要があるだろう。国民の健康意識の高まりもあり、健康経営へ取り組む企業も増えていることから、加入者および母体企業からの保健事業に対する理解が得やすくなっており、新たな保健事業も行いやすくなっているのではないだろうか。医療費の抑制は一朝一夕ではいかず、時間はかかるが、国全体の問題であり、粘り強く取り組んでいく課題である。
次に、高齢者医療制度の問題である。高齢者医療制度は、国費の一部を健保組合等の被用者保険に転嫁する構造となっており、この負担構造改革は喫緊の課題である。これには、政府への要望とともに、世論の形成も必要であろう。健保連を中心に、全健保組合が一丸となり、経団連等の関係諸団体を巻き込みながら、今まで以上に効果的な広報活動を行うことが求められる。健保組合の財政が危機的状況で、その主な要因が高齢者医療制度への拠出金であることを強く訴え、早急に制度改革を実現する必要がある。
今年4月から働き方改革関連法が施行され、政府は、1億総活躍社会、生涯現役社会を目指すとうたっており、間もなく100歳時代が来るともいわれている。高齢者医療制度について、高齢者の定義を含め、根本的な再検討が必要ではないだろうか。 |
| |
(S・K) |
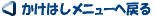 |
 |
|
 |