 |
| 健保連大阪連合会は9月6日、大阪市福島区の新梅田研修センターで、「健康経営セミナー」を開催した。この催しは、健保組合と事業所とのコラボヘルスや健康経営優良法人認定制度などの取り組みへの対策として、有識者からの情報を取り入れてもらおうというもの。健保組合、事業所担当者ら165人が参加。産業医科大学 産業生態科学研究所 産業保健経営学 教授の森晃爾氏、健保連本部 保健部長の小松原祐介氏による講演が行われた。 |
 |
 |
 |
 |
| 森口 氏 |
開催に先立ち、健保連大阪連合会 保健共同事業委員長の森口氏(塩野義健保組合 常務理事)のあいさつがあった。森口氏は、「健康経営は従業員の健康の維持・増進が企業の生産性や収益性の向上につながる。経営的な視点から、従業員の健康管理を戦略的に実践する、言わば、生産性の低下を防ぎ、医療費を抑え、企業の収益性向上を目指す取り組みである。保険者である我々が実施しているデータヘルスと、企業が実施する健康経営が車の両輪のように機能することで、保険者が国から求められているコラボヘルスを実現することができる。コラボヘルスにより、保険者と事業主が積極的に連携し、明確な役割分担と良好な職場環境のもと、加入者の疾病予防・健康づくりを効果的・効率的に実行することで、健康経営をより一層推進させることも可能である」と述べた。
 日本の将来人口推計を踏まえ、健康経営を進める意義として「少子高齢化等により労働力が限られていくなか、人材投資はすべての組織にとって持続的成長のカギ。人材投資を通じた従業員の健康増進に取り組む意義を普及させることで、経済の持続的成長と同時に、“生涯現役社会”の構築を目指す」とした。
日本の将来人口推計を踏まえ、健康経営を進める意義として「少子高齢化等により労働力が限られていくなか、人材投資はすべての組織にとって持続的成長のカギ。人材投資を通じた従業員の健康増進に取り組む意義を普及させることで、経済の持続的成長と同時に、“生涯現役社会”の構築を目指す」とした。
健康経営の前提は、「社員の健康を経営の基盤として位置づける」ことであり、経営者の従業員の健康に対する想いが重要となる。経営者自身の時間の投資や健康担当に執行役員を任命すること、人的・金銭的投資などの経営理念や方針を見直し、経営レベルでの会議における議論や保険者との連携など、組織体制の見直しも必要である。
 |
| 森 教授 |
健康経営を進めるにあたって苦労しているのは「評価」の部分である。これは、評価の仕方を計画に入れておらず、「何を目指すのか」という基本方針がはっきりしていないためであり、目標を数値化することが重要である。
健康経営におけるコラボヘルスについては、健保組合と企業の連携が大切である。しかし、両者の保健事業における目的が異なり、活動の優先順位が一致しないことがある。そこで、健保組合と企業とが計画を作る段階から共に検討を行うなど、両者で共通認識をもつことが求められる。
そして、「健康経営は、『社会』の要請から始まったものであるが、『企業』にとっても『働く人』にとっても、それぞれの持続可能性を通して、社会の持続可能性の向上に貢献できるもの。その決め手は、『働く人』および『企業組織』のヘルスリテラシーの向上であり、“健康経営”に段階的に取り組み、自己健康管理ができる生産性の高い社員と、それを育む組織の構築を目指し、企業文化として定着させることである」とまとめた。

| 「健康寿命延伸に向けたデータヘルスと健康経営」
小松原部長 |
 |
| 小松原 部長 |
健康寿命とは、日常生活に制限のない期間を指し、2016年では男性72.14年、女性74.49年である。日本は平均寿命が世界一であるが、健康寿命との差は約10年。健康寿命を延伸し、平均寿命との差を如何に小さくするかが重要である。
保険者に課せられているデータヘルス計画とは、レセプト情報と特定健診結果を用いて、データ分析に基づき効率的・効果的な保健事業を展開するものである。加入者の健康づくり・疾病予防は、保険者にとって重要な責務であり、データヘルス計画は、そのための1つのツールである。しかし、高齢者医療制度への拠出金が増加しており、健保組合における保健事業費は減少を続けている。限られた予算のなかで、どのように取り組むかが重要となっている。
また、健康経営に関する顕彰制度も創設されている。健康経営にかかる各種顕彰制度を推進することで、優良な健康経営に取り組む法人を「見える化」し、従業員や求職者などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる企業」として、社会的に評価を受けることができる環境が整備された。特に、就活生とその親は就職先に対し、「従業員の健康や働き方に配慮している」かどうかを重視しているという調査結果がみられた。
コラボヘルスにおいて最も取り組みやすいと思われるのは喫煙対策である。喫煙による労働時間のロスで、どれだけのコスト負担が生まれるのか。加えて、喫煙していると特定保健指導における積極的支援に該当する可能性が高まる。積極的支援と動機付け支援の費用差も負担増となる。例えば、喫煙率の低下を目指し、就業時間中の禁煙外来への受診を認めるなどの取り組みを行っている企業もある。
これらの健康経営やデータヘルスにより、疾病予防・重症化予防がなされれば、医療費の適正化にも寄与する。さらに、健康な高齢者が増えるということは、働く世代の年齢も引き上げられ、高齢者にも「支えられる側」から「支える側」に加わっていただける。これにより、国民皆保険を次世代につなぐことも可能となる。 |
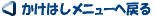 |
 |
|
 |