 |
 |
昨今、AI(人工知能)という言葉をよく耳にする。AIといえば、最新技術というイメージだが、実は1950年代から研究が続けられており、現在のビッグデータやディープラーニング(深層学習)を活用したAIは「第三次人工知能ブーム」といわれる。身近では、スマートフォンの音声認識や障害物を避ける自動運転、産業分野のロボット制御など、さまざまな場所にAIが活用されている。医療や健康分野においてもAIを使ったデータ分析が行われており、それが現在推進しているデータヘルス計画にもつながる。
データヘルス計画も第2期に入り、データ分析や活用のノウハウ蓄積が進みつつあるように感じる。医療分野でもAIの利用が活発になっており、専門医でも難しい病気を発見し命を救ったということが話題になったりしている。
医療技術の高度化は医療費の増加の一因ともいえるが、新たな診断方法や治療方法の確立、疾病の予防策につながれば増加抑制効果としても期待できる。ビッグデータやAIが先進的な医療技術の普及や適切な健康管理に役立つ時代がすぐ近くにきているように感じる。
話は変わるが、これまで団塊の世代が75歳以上になる2025年を焦点に議論がなされてきたが、次の焦点として団塊ジュニア世代が65歳以上の高齢者となる2040年がクローズアップされている。社会保障制度の持続が困難さを増すため、(議論がわかれる問題ではあるが)消費税率のさらなるアップや年金受給時期の繰り下げ、高齢者の雇用の問題、社会保障費の負担問題等々、さらに踏み込んだ議論や取り組みが必要と思われる。
我々が直面している高齢者医療費の負担問題については、キーワードは公平性と考える。ここ数年、公平な負担=負担能力に応じた負担ということが強調され、その結果、後期高齢者支援金や介護納付金に総報酬割という仕組みが導入され拡大してきている。
負担の公平については、高齢者と現役世代の観点からの公平、税負担と社会保険負担の観点からの公平、報酬水準に応じた応益負担と受けるサービスに応じた応益負担という観点からの公平―等々がある。大切なことはこれに代表されるような重要課題について政治の場において、与野党ともに真正面から受け止め、しっかり議論をして国民全体が納得できるものを導き出してほしいと願う。
社会の変革や技術革新のスピードは激しいが、変化が速いからこそ問題の本質をしっかり見極める目を持ち、持続可能な社会保障制度の再構築に向けて中長期的な視点から議論・行動していく必要がある。しっかり『深く学習』しながら。 |
| |
(K・M) |
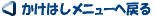 |
 |
|
 |