 |
いま そこにある危機

― 確実に来る平成37(2025)年度 ― |
この時評が皆さんの目に触れるのは、平成28年度の概算医療費総額が厚生労働省から発表されるころだと思います。27年度の医療費総額は42兆円で、どの程度の増加になるのか。案外増えていないのではとの見方もあるようです。
先に目を移せば、いわゆる団塊の世代が75歳以上になる37年度が注目されています。そのときの医療費は、厚労省のホームページに掲載されている資料をみると、54.8兆円になるとの試算もあり、また、60兆円を超える試算もあります。
健保連本部でもシミュレーションを行っており、それによると、後期高齢者医療費が、27年度の15.2兆円から37年度には25.4兆円になり、医療費全体は57.8兆円になるとの試算です。
27年度から約16兆円増加することになります。あくまで試算とはいえ、この程度の増加は覚悟しておく必要があります。
その財源としては、31年10月に予定されている消費税増税による税収増が期待されます。とはいえ、消費税率の8%から10%へのアップによる税収増は5〜6兆円の見込みです。医療費のほかにも、年金や介護、教育、子育て支援など少子化対策の分野でも、財源が必要でしょう。2%の増税では、医療費をはじめとする将来の社会保障関係費用を賄うには不十分との感は否めません。さらなる増税が必要といわれる理由です。
その消費税率2%アップは、過去2度、延期されました。経済情勢、いわゆる景気に配慮したものです。一方、高齢者医療の拠出金の増加により、悪化する自らの財政を維持するため、健保組合では保険料率をアップしてきました。
こうした健康保険料をはじめとする社会保険料の負担増により可処分所得が伸びない、伸びが鈍いことが消費者心理に影響し、景気に少なからずマイナスの影響を与えているとの見方があります。経済の動きの難しいところです。
もちろん、37年度に向けては、消費税率アップだけでなく、薬価を含む医療費の抑制や、高齢者の本人負担の見直しなどの改革も必要でしょう。ただ、薬価の動きは、製薬メーカーの経営や新薬の開発意欲に関わります。高齢者の本人負担増には反発があるでしょうから、丁寧な説明が必要です。
また、健保組合においては、将来の医療費適正化に向けた保健事業など、自らができることを地道に行っていくことが必要であると認識しています。一方、財政面、人的面での制約があるのも事実です。
どれをとっても、簡単な道のりではありません。しかし、停滞は許されず、前に進まなければなりません。
37年度まで8年、まだ時間はあるように思えますが、いまから8年前の21年度は、政権交代があり、事業仕分けが世の中の話題になった年です。そのときから現在までの8年間を振り返ると、将来に明るさが見える改革、改善があったとは思えません。37年度問題、“いまそこにある危機”です。
皆保険制度を維持し、次世代に引き継ぐため、健康保険組合がこれまで行ってきた、また、これからも行う、改革に向けた要望、提案を、国は真剣に受け止め、早期に実現を果たすことを望むものです。 |
| |
(A・K) |
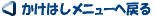 |
 |
|
 |