| ●量より質 |
| |
私は、健康保険組合の保健師として、加入者の疾病予防・健康保持増進の業務に携わっている。業務の1つである特定保健指導のポイント制について、以前から思うことがある。
医療・保健の分野では、対象者に合わせた個別性のあるケアは基本中の基本であり、学生時代、耳にたこができるくらい教わってきた。また実際に、多くの対象者のケアを通して、個別性の重要性を感じてきた。
それなのに、特定保健指導はポイント制という枠組みがあることで、対象者に合わせた個別性のあるケアをやりづらくしている。専門職にかまってもらったら改善できる人、かまってもらわずに自分の力で改善したい人など、対象者によって個性があり、介入方法が変わってくるのである。しかし、例えば、かまってもらわずに自分の力で改善したい人に、6カ月後の評価までの間に面談指導や文書指導をして、ポイントを稼いでいるのが現状である。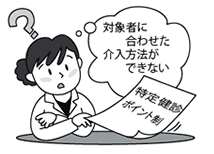
このように、対象者に合わせた介入方法ができないので、結果がついてこないケースがあるのも当然だ。何のための特定保健指導なのだろうとわからなくなることがある。特定保健指導は、対象者に合わせた個別性のあるケアを行い、生活習慣病を未然に予防し、対象者のQOL(生活の質)向上、生活習慣病に占める医療費の適正化を目指すものなのではないのだろうか。だとすれば、特定保健指導の実施状況をポイントという介入の量で判断するのではなく、改善率という介入の質で判断し、ペナルティを課すべきであると私は考える。
来年度から始まる特定保健指導第3期では、より質(結果)を重要視した制度になることを期待する。
(第1地区 K・N) |
| |
|
| ●真夏の夜の夢 |
| |
203X年、すっかり後期高齢者の一員となり、病院が家に次いで落ち着く場所になってしまった。
以前は、2割だった医療費の患者負担が3割になり、どの年代も原則、同じ負担率になっている。「払う能力のある人がより多く支払う」、いわゆる総報酬割が導入されて久しく、高い収入がある高齢者はさらに負担が多くなった。
現役の時に勤務していた××健保組合は、ほかの健保組合とともに協会けんぽに統合されて○○健康保険グループになり、なんとか国民皆保険は維持されている。昔、一生懸命に訴えていた高齢者医療費の負担構造の問題は、高齢者が多くなりすぎて制度が成り立たず、高額療養費の限度額を引き上げるなど被保険者に直接負担を求める割合が高くなっている。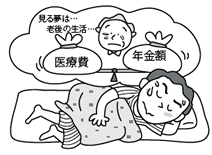
今や年金でもらう額と医療費で支払う金額の差がどんどん縮んできた。医学の進歩で80代、90代が増え、70代まで働くのも普通になったが、健康だから働いているのか、病院に通うために働いているのか、わからない状態だ。
教育費や趣味嗜好にかけられる費用が減るかわりに、医療費の割合が増え、結局、可処分所得は増えていない。「健康寿命の延伸」や「生涯現役社会」の実現は果たして幸せだったのか――。
そうつぶやいたところで目が覚めた。ああ今日も骨まで溶けるような1日になりそうだ…。
(第2地区 T・A) |
| |
| ●高齢者の定義とは? |
| |
年初に「日本老年学会・日本老年医学会」から、高齢者の定義と区分に関する提言がだされました。皆さんの記憶のひとつにも残っていると思います。この提言では、高齢者について、10〜20年前と比較して加齢に伴う身体的機能変化の出現が5〜10年遅れる、 「若返り」現象が起きているとして65〜74歳を 「若返り」現象が起きているとして65〜74歳を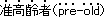 に区分しています。現に、「平成26年度高齢者の日常生活に関する意識調査」でも、65〜69歳の方で自身が高齢者ではないと感じている方々が、実に72%もおられます。 に区分しています。現に、「平成26年度高齢者の日常生活に関する意識調査」でも、65〜69歳の方で自身が高齢者ではないと感じている方々が、実に72%もおられます。
私が通うスポーツセンターでも な高齢の方もわんさかおられますし、皆さん笑顔で、汗をかいてスポーツを楽しんでいます。そんな光景を見ると、事業主とのコラボヘルスを活用して、健康維持・増進のサポートを積極的に行い、1人でも多くの元気な准高齢者を社会に送り出す事が、我々健保の責務と痛感する今日この頃です。 な高齢の方もわんさかおられますし、皆さん笑顔で、汗をかいてスポーツを楽しんでいます。そんな光景を見ると、事業主とのコラボヘルスを活用して、健康維持・増進のサポートを積極的に行い、1人でも多くの元気な准高齢者を社会に送り出す事が、我々健保の責務と痛感する今日この頃です。
ちなみに、「ローリングストーンズ、平均年齢73・5歳」今だ現役!
(第3地区 Y・S)
|
| |
投稿規定 |
「言わしてんか!聞いてんか!」 |
| ■ |
500字以内。手書き、ワープロ自由。見出しも付けてください。原稿を添削する場合があります。 |
| ■ |
イラスト、写真も歓迎します。 |
| ■ |
原則として、投稿者の「所属組合名と実名」を掲載。匿名希望(イニシャル)の場合も、原稿には「所属組合名と実名」を明記してください。 |
| ■ |
原稿は地区会の広報委員へ送ってください。 |
| ■ |
問い合わせは、健保連大阪連合会事務局へ。(06-4795-5522) |
|
|
|
| |
|
|