 |
うつ病を知る
〜多様化するうつ病とその対応〜 |
| 10月9日、大阪商工会議所で心の健康講座を開催。近畿大学医学部 精神神経科学教室 白川 治教授が「うつ病を知る〜多様化するうつ病とその対応〜」をテーマに講演されました。参加数は、52組合・75人。(以下に講演要旨) |
 |
| |
 |
| |
白川 治 氏 |
うつ病は、100万人の時代とされ、ごく身近なこころの失調として認知されてきましたが、最近では、多様化に対する診断と対応が求められています。
中核的(内因性・メランコリー型)うつ病の診断と治療・対応
中核的なうつ病では、自分を責めたり、自分はダメな人間だと思う気持ちがおこってきます。このような自責感・自己否定感がひどくなると、自殺に至る場合があります。
うつ病の兆候として、「朝気分が重く、仕事に行く気力が出ない」、「なにごとに対しても億劫になる」、「なにをしてもおもしろいと感じない」、「夜中になんども目が覚め、早朝にはもう目がさえてしまう」、「食事がおいしくない」といった症状があります。
うつ病への気づきとしては、「好きなことを楽しめているか」「夜眠れているか」に着目することが大切です。中核的なうつ病の治療では、休養と抗うつ薬が効果的ですが、再発することも多いので、再発防止の手立てを考えておく必要があります。服薬の継続に加えて、生活状況のなかにうつ病再発の要因を見出し、それに対処する方法を考えるようにしましょう。
うつ病概念の拡散と現代的な"うつ"の理解
うつ病概念拡散の要因としては、DSM、ICDのような国際的な診断基準の普及・定着があります。こうした診断基準では、従来の内因性概念は消滅したため、内因性うつ病に代わって心因性(反応性)うつ病がうつ病の中核とみなされる傾向が顕著となり、うつ病と適応障害との境界も曖昧となりました。
また、うつ病にとどまらず、不安障害をも射程にいれたSSRIといった新たな抗うつ薬の登場が与えたインパクトも見逃せません。
活発な啓発活動により、うつ病の社会的認知度は飛躍的に向上し、スティグマは軽減するなかで、軽症のこころの失調の診断と治療で主役となる精神科診療所が増加しました。これによって、精神科受療に対する敷居は低くなりました。
とくに、若年者が挫折や不適応を契機に気分の落ち込みを自覚し、治療を求めるケースが増えてきています。
価値観の多様化、倫理規範の弱体化等によりうつ病の病前性格が変容し、自責に向かうエネルギーが、他罰に向かう傾向が顕著となった時代的な背景のなかで、パーソナリティ成熟ないしは社会的自立の過程にある若年者が受療するわけです。従来の真面目かつ几帳面で仕事熱心な中年における発症を、うつ病のプロトタイプとして構築されてきた治療論が通用しないのも当然かもしれません。
単極性うつ病と双極性障害の境界が曖昧になり、双極スペクトラム概念が提唱されるに至っているのも、こうした時代的な背景が深く関わっているように思います。
一方、1990年代後半からおきた労働環境の変化(終身雇用制・年功序列制の終焉、裁量労働制の普及、成果主義の台頭、グローバル化・IT化による労働者に求められるスキルの高度化等)が、うつ病をはじめとするこころの失調を新たに生み出している可能性についても考慮しておく必要があります。
うつ病に求められる対応
うつ病はひとつの病気ではなく、病態、経過の異なる抑うつ症候群と考えておくとよいでしょう。
うつ病の治療では、薬物療法(抗うつ薬など)、精神療法(認知療法など)、環境調整が3本の柱となります。中等症以上のうつ病では、薬物療法と休養が大切です。しかし、非内因性・非メランコリー型のうつ病が大半と考えられる現代型"うつ"では、薬と休養という疾病性の強調よりもむしろ、パーソナリティなどの個人要因や職場環境などの環境要因の重視、評価が大切です。
とくに、若年者では、自立や成長、さらには脱皮を意識した精神療法的なアプローチが求められることも少なくありません。 |
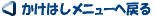 |
 |
|
 |