| |
|
| ●禁煙のすすめ |
| |
飲みに行ったときにカッコをつけて20歳から吸い始めたタバコ、毎日20本は吸っていた。
気がつけば、親戚で私以外にタバコを吸う人間はいなくなり、お正月に皆で集まっても1人だけタバコを吸うために寒空の庭に出ている。
妻と一緒に旅行に行っても、私は、まずはタバコが吸える場所を探し、ちょっと時間があれば「吸ってくる」と席を離れるので、妻からは、ちっとも楽しくないと文句をいわれる始末。
妻と本屋に行ったあるとき、「これでタバコをやめた」と兄がいっていた本があった。
「まぁ、だめもとで買ってみるか」とレジに行きかけたら、妻が「中身は同じだから新刊じゃなくて古本で十分」って100円の古本をみつけてきた。
100円でタバコがやめられる訳がないと思っていたけれど、出だしから「読み終わるまでタバコをやめないでください」と書いてあるので、タバコを吸いながら気楽に読み始め、最後まで読んでしまっていた。読み終えたら、禁煙という意識はまったくなく、普通にタバコなしで過ごしていた。あれほど怖がっていたニコチン中毒って? タバコが意識の外にいってしまっていた。
確かに本の効果はあったのだろうけれど、「構えず自然体で意識しない、禁煙するんだといって頑張らない」。私の場合は、新刊ではなく100円の古本から始めたのがよかったように思える。
タバコをやめて1年後、昨年の夏に健保の仕事をすることになった。今年は禁煙サポート制度を始めようと思う。ちょっとしたきっかけで禁煙はできる。そのちょっとしたきっかけを作れたら幸いです。
(第4地区 N・T) |
| |
|
| ●新アクティブ世代 |
| |
先日、海外のリゾート地へ張り切って旅立ち、真っ青で綺麗な海や空の下、ポリネシアンダンスにシュノーケリング、ジャングル探検、と果敢に挑戦し、リフレッシュしてきました。
でも、そこで出会った高齢者の方がたのパワーに押されっぱなしの旅となりました。
「2012年 団塊の世代全員が前期高齢者へ」。思い起こせば、国内外問わず、旅行に行くと、元気な高齢者の方の姿が目につきます。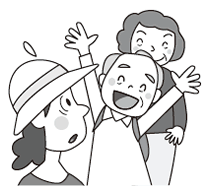
「年間医療費38兆5850億円。この6割を65歳以上の高齢者医療費が占めている」なんて考えられません。元気の秘訣は、じゃあ、なんだろうと、私なりに考えてみました。やっぱり「〜がしたい」という気持ちが強いのでしょう。
旅行! おいしいゴハン! あれも! これも! という気持ちがいっぱいあれば、病気にかかる暇がなくなるのかなと。もちろん、お財布とも大いに相談、仲良くすることが必要ですが、皆さまもなにかに挑戦したいという気持ちを持って、今年1年、元気に過ごしていきましょう!
(第5地区 スナフキン) |
| |
| ●高額療養費について |
| |
多額な自己負担額を軽減してくれる高額療養費制度。限度額適用認定証により現金給付が減ったとはいえ、相次ぐ制度改正で仕組みが難しくなり、担当者としては頭痛の種です。
70歳以上・未満の区分と、上位・一般・非課税の所得区分、多数該当、レセプト単位での計算と合算対象。面倒なのが8万0100円という中途半端な数字、プラス(医療費マイナス26万7000円)の1%負担部分。これらの被保険者への説明にひと苦労します。8万0100円は平均標準報酬月額の25%だとか、1%の定率負担部分は要した医療費に応じた負担であるとの理屈。
しかし、限度額適用認定証を利用して窓口精算すると、被保険者は食事療養費の自己負担や自費分と合わせて支払うので、3割がいくらで高額療養費がいくらという認識もないまま退院してしまいます。果たして意味があるのかなぁと疑問です。
担当者としては、限度額適用認定証の発行事務や算定基準額の説明に加え、特定疾病・疾患や地方単独医療制度もからむと、さあ大変。さらに高額介護合算なるものも。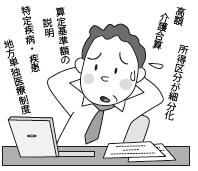
このような制度を、病みあがりや看護疲れの被保険者に、理解しろというのは酷なもの。厚生労働省のご担当者様、一定の理論や整合性がないといけないのもわかりますが、「やさしさ・わかりやすさ」というのも制度づくりの大きな要素だと思います。
えっ、所得区分が細分化される? 高齢者の自己負担割合が引き上げられる? しかも、段階的に? "じぇじぇじぇ…"いや もう "ごちそうさん"
(第6地区 R・A)
|
| |
|
投稿規定
|
|
「言わしてんか!聞いてんか!」
|
| ■ |
500字以内。手書き、ワープロ自由。見出しも付けてください。原稿を添削する場合があります。 |
| ■ |
イラスト、写真も歓迎します。 |
| ■ |
原則として、投稿者の「所属組合名と実名」を掲載。匿名希望(イニシャル)の場合も、原稿には「所属組合名と実名」を明記してください。 |
| ■ |
原稿は地区会の広報委員へ送ってください。 |
| ■ |
問い合わせは、健保連大阪連合会事務局へ。(06-4795-5522) |
|
|
|
| |
|
|