| |
|
| ●最近思ったこと |
| |
8月に社会保障制度改革国民会議の報告書が示されましたが、その内容は、高齢者医療制度を支えるための拠出金負担に苦しんでいる健康保険組合の、厳しい財政状況に関する認識がまったくないものでした。
本当に待ったなしの高齢者医療制度の見直しを、また先送りにし、この制度の将来像を示していただけるかという期待感をも打ち崩す内容といわざるを得ないものでした。
一方、9月の敬老の日に発表された65歳以上の高齢者は3186万人。総人口に占める割合が25%に達し、4人に1人が高齢者ということです。今後、2035年には、65歳以上の高齢者の割合は33.4%となり、3人に1人が高齢者になると推計されています。まさに、老人天国になりつつあります。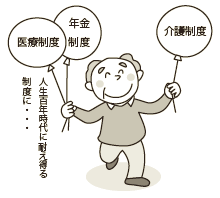
郷里の岡山の平櫛田中(ひらぐしでんちゅう)さんという著名な彫刻家は、「六十・七十は鼻たれ小僧、男盛りは百から、百から」と言われています。せっかく延びた寿命ですので、できれば生き生きと元気にゴルフ三昧し、毎日晩酌を楽しみつつ過ごしたいというのは、誰しもが抱く夢です。
医療・年金・介護の制度が、人生百年時代に耐え得る制度となるよう切に願う次第です。皆さんもそう思いませんか。
(第4地区 M・K) |
| |
|
| ●目指せ!気配り上手 |
| |
先日、病院に行ったときのことです。待合のソファに座っていると、突然、看護師さんらしき女性の大きな声が聞こえてきました。「いつから痛むの?」「食事はいつごろ?」「便は出ていますか?」等々と、問診が始まり、その声は病院の待合にいるすべての人に聞こえるボリュームでした。
何度も繰り返される『公開問診(?!)』は、患者の名前はもちろん問診内容すべてがオープン。その声がする方をみると、高齢の男性の姿が…。1人で初診に来られたようで、男性は耳が聞こえにくい様子でした。
問診の声が大きくなる状況は理解したものの、はたして、この方法しかないものか、もう少しプライバシーを意識できないものか、と不思議な気分になり、また、何年後かに私もあのように問診を受けるのか、と想像すると悲しくも感じました。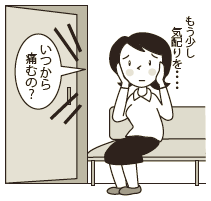
「医療現場」という、日々、生死に関わる仕事で大きな声は欠かせないものだと思います。しかし、いまどきは、個人の名前ではなく「番号」で呼ぶ病院があるように、もう少し状況に配慮した対応をして欲しいと感じました。また、「いつもの習慣」は、場合によっては周囲に受け入れ難いことになるものだな、とあらためて感じた出来事でした。
長い間、健保組合の仕事を続けていると、被保険者からの質問に対して「いつもの習慣」で健保独特の用語をサラッと押しつけてしまいそうな自分に、ときどきヒヤッとします。いま一度振り返り、相手の状態に気配りし、場面に応じて配慮する力を高めたいと思います。
(第5地区 S子・Y) |
| |
| ●思いつくまま |
| |
社会保障制度改革国民会議の最終報告が8月はじめに首相に手交され、その中身について、さまざまなコメントが発表された。
ちなみに健保連は、「われわれの期待を大きく裏切る結果となった」とした。
常日頃のさまざまな場で、「わが国の社会保障制度の中核を担う健保組合は…」「健保組合の役割はその保険者機能を十分に発揮して…」との冠詞付きで述べられる。
はたして「担っている」「発揮しようとする」当該健保組合の周辺事情はいかがなものだろうか。
語られて久しく、かつ喫緊の課題でもある「支援金・納付金」。確固とした財源の確保なしに、健保組合に対し応分以上の負担金を強いるものである。
いわゆる「アベノミクス」効果により、景気は回復しつつあるとのことだが、現時点で全産業に波及しているとはいえない。とりわけ総合健保組合の母体である中小企業では実績として表れるまでに至らず、賃金・賞与は足踏み状態にある。結果、保険料収入は伸び悩み、一方、天井知らずの支援金・納付金と医療費増の捻出に追われ、保険者機能の十分な発揮どころではないのが現状である。
日々保険料率の算段に追われる始末だが、この時期の引き上げは多くの事業主の理解を得るに難く、健保組合の負担はすでに我慢の限界を超えている。
中核を担うにふさわしい、保険者機能を十分に発揮していると胸を張れる健保組合になろうと努力するわれわれに、行政の真のサポートを期待する。
国民の健康を守らねばならないのは、またその意識を高めなければならないのは最終的にいったい誰なのか。
もっと腰を据えた、将来を展望した方針に基づく、給付と負担のバランスのとれた持続可能な医療保険制度の早急な構築を切に願うところである。
時間がないのである。
(第6地区 Y・I)
|
| |
|
投稿規定
|
|
「言わしてんか!聞いてんか!」
|
| ■ |
500字以内。手書き、ワープロ自由。見出しも付けてください。原稿を添削する場合があります。 |
| ■ |
イラスト、写真も歓迎します。 |
| ■ |
原則として、投稿者の「所属組合名と実名」を掲載。匿名希望(イニシャル)の場合も、原稿には「所属組合名と実名」を明記してください。 |
| ■ |
原稿は地区会の広報委員へ送ってください。 |
| ■ |
問い合わせは、健保連大阪連合会事務局へ。(06-4795-5522) |
|
|
|
| |
|
|