| |
|
●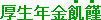 |
| |
昭和54年5月に、私が当健康保険組合に就職して以来、早や34年が過ぎました。
入社間もない新米職員の私は、総務の先輩から「うちの組合は厚生年金基金に加入しているから年金をもらうときに、基金の分がプラスα上乗せされるので、いいで!」といわれたことをよく覚えています。その当時は私も若かったので、年金の受給は36年後で、深く考えることもありませんでした。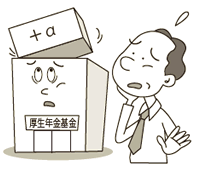
ところが、何年か前に、基金の資産が枯渇し、私が年金をもらうときには基金のプラスαの上乗せ分が3分の1に減額されるというのを聞いて、がっかりしました。
平成24年2月にAIJ投資顧問の年金消失事件がニュースになり、あっという間に厚生年金基金制度を見直す改正法が可決され、平成26年4月施行となりました。私が加入している基金はAIJには関与していなかったのですが、現在、解散に向けて動き始めています。
基金の掛金は全額事業主負担ですが、解散が決定するまで掛金を掛け続けるなんて、なんと無駄で腹立たしいことでしょう。基金が解散すると、基金のプラスαの部分はゼロになるわけであり、いっても仕方のないことですが、将来に破綻するような「基金制度」を認めた国に腹が立つ。
(第4地区 T・N) |
| |
|
| ●単式簿記(現金主義)について |
| |
私にとっては、組合会等で、巨額な高齢者医療制度の納付金の算出方法を説明するのがひと仕事で、この時期になるといつも頭を悩ませています。
もう1つが、単式簿記の説明です。通常の企業の複式簿記では、収入と支出の差額が資産の増減に反映されており、「収支差額(期間損益)」が、「財産の増減額」を意味しています。
私は、今年の決算の収入支出説明では、概要表(その2)の「収入支出決算」に「繰入金等の調整の特別欄」を新設し、「財産の増減額」に連動するよう特別な資料を作成しました。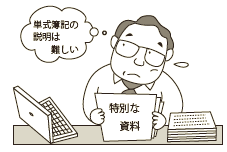
そして、「健保の収入簿・支出簿は、家計簿の収入・支出のようなもので、財産の増額を示していない。強いていえば、概要表(その2)の『経常収入支出差引額』が、財産の増減の概算額を表していますが、複式簿記の経常損益とはまったく異なります」と説明しました。
組合会以外で、私の頭を悩ませていることは、新任の監事への決算の締切日の説明です。
複式簿記では、3月末に未収・未払を計上し3月末の銀行残高で説明できます。単式簿記では、収納は5月末まで、支出は4月末までです。つまり、当年度と翌年度が混在しています。皆様は、どのように説明されていますか?
(第5地区 N・K) |
| |
| ●「適用拡大」に関して |
| |
平成28年10月から厚生年金・健康保険の加入者が、週20時間以上の短時間労働者も加入対象とされる。当健保では約4000人が該当し、被保険者数は現在の2倍以上になる見込みである。
報酬月額が低く、年齢層も高い。当健保は一般保険料率10%、介護保険料率2%、合計12%。22年度以降、料率の引き上げ、付加給付の廃止、人間ドック助成金の見直し等を行った。その結果、健保組合のメリットは人間ドックの一部補助のみで、皆無に等しい。
別途積立金も枯渇し、「法定給付費等に要する保険料率」は23年度10.35%、24年度10.89%。これでは保険者機能は発揮できない。
平成25年度は高齢者医療制度への支援金等が少し減ったため、「法定給付費等に要する保険料率」は10%を少し切り、一息ついたところで「適用拡大」。実施されれば当健保は解散確実の状況に至る。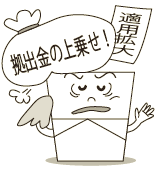
インターネットをのぞくと、「健康保険に加入すれば、病気で会社を休み給与がもらえないときは傷病手当金が支給される」と被保険者にとって都合のいいことが掲載されている。
この適用拡大は、「年金財源確保」から端を発したのではないだろうか。
年金財源確保のためならば、年金分野で考えていただきたい。適用拡大が実施されると、健保組合には高齢者医療制度の拠出金の上乗せが回ってくる。特例を設けるとも聞いているが、すぐに本則に戻るであろう。
保険料の46%が高齢者医療に回され、8割以上の健保組合が赤字という現状を考慮せず、特定健診や特定保健指導の義務付けや、被扶養者が請負労働でケガをしたときの健保適用等、これでは健保組合の解散が増加すると考えるのは私だけだろうか・・・。
(第6地区 Y・K)
|
| |
|
投稿規定
|
|
「言わしてんか!聞いてんか!」
|
| ■ |
500字以内。手書き、ワープロ自由。見出しも付けてください。原稿を添削する場合があります。 |
| ■ |
イラスト、写真も歓迎します。 |
| ■ |
原則として、投稿者の「所属組合名と実名」を掲載。匿名希望(イニシャル)の場合も、原稿には「所属組合名と実名」を明記してください。 |
| ■ |
原稿は地区会の広報委員へ送ってください。 |
| ■ |
問い合わせは、健保連大阪連合会事務局へ。(06-4795-5522) |
|
|
|
| |
|
|