 |
働きがいのある職場づくりでメンタルヘルス対策

~ 従業員支援プログラム(EAP)の実際 ~ |
| 7月30日、薬業年金会館で心の健康講座を開催。関西福祉科学大学 健康福祉学部(大学院 社会福祉学研究科) 長見まき子准教授が「働きがいのある職場づくりでメンタルヘルス対策~従業員支援プログラム(EAP)の実際~」をテーマに講演されました。(以下に講演要旨) |
 |
| |
 |
| |
長見 まき子 氏 |
日本の労働者のメンタルヘルスは深刻な状況が続いており、多くの事業場ではメンタルヘルス対策の推進を産業保健活動の重要課題と位置づけています。メンタルヘルス対策推進に関わるさまざまなガイドラインが行政から出されているものの、事業場内のマンパワーだけでそれを推進できるところは限られ、事業場外資源を活用して推進することになります。
EAPは事業場外資源のひとつですが、単なる心理相談機関にとどまらない、労働者のパフォーマンスや組織の生産性の向上を目指す先進的なプログラムであり、産業保健分野において事業場外資源の重要な一角を担うものとして期待が寄せられています。

2―1.EAPの歴史
EAPは1950年代に米国で開始した職場のメンタルヘルスサービスで、「従業員支援プログラム」と訳されています。日本へは1980年代に紹介され、当初は「外部の相談窓口」的なサービスとして利用されていました。しかし、2000年にメンタルヘルス指針が厚労省から公表されると、EAPは継続的にシステム化されたメンタルヘルスサービスを提供可能な事業場外資源として注目され、大企業を中心にEAPの導入が広がりました。現在では労働衛生機関、医療法人、NPO法人などがEAP機関を設立し、100超のEAP機関が活動しています。
2―2.EAPの目的
EAPの目的は、労働者の個人的な問題に起因するパフォーマンス(生産性・業績)の低下に対し、その原因を明らかにして解決することを支援し、職場でのパフォーマンスを維持・向上させることです。したがって、医療、福祉、産業保健活動とは目的が完全に同じではありません。
個人的な問題の中心はメンタルヘルス不調ですが、家庭問題、経済的問題などがパフォーマンスに影響を与えていると判断される場合は解決支援の対象となります。さらに、労働者個人と同様に、組織や職場が生産性に影響を与える問題(リストラなど)の解決に取り組む際にも専門的支援を行います。
2―3.EAPの基本的機能
EAPの基本的な機能としては、労働者のパフォーマンス低下の背景となる問題を同定し(アセスメント)、問題解決のための最適な資源につなぐ(紹介、連携)ことです。従来は2次予防や3次予防としての個別対応が中心でしたが、職場環境改善などの組織へのアプローチも強調されてきました。
2―4.EAPの特徴
他の専門機関とは異なるEAPの特徴は①職場を基盤としたサービス、②利用にあたっての抵抗感の軽さ、③事業場との連携、④1次予防から3次予防までの一貫したサービス、⑤個人と組織へのコンサルテーション機能などがあげられます。これらの特徴をいかしてEAPを活用すれば、事業場内のスタッフを中心としつつ、低コストで多彩なメンタルヘルス対策を展開することが可能になります。

EAPの活用はメンタルヘルス対策の強力な推進力になることは間違いありませんが、その効果を生み出すのは運用の仕方にかかっています。EAP機関にメンタルヘルス対策を丸投げするのは禁物です。メンタルヘルス対策の主体はあくまで事業場にありますので、定期的な効果評価と連携が大事です。EAPをうまく活用し、年々発展するメンタルヘルス対策を目指しましょう。
注:EAP(Employee Assistance Program) |
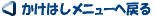 |
 |
|
 |