 |
 |
2008年の合計特殊出生率(1人の女性が生涯に生むと推定される子どもの数)は、前年に比べて0・03ポイント高い1・37と、3年連続で上がった。これは、「婚活ブーム」や企業の育児支援の拡充などが追い風になったようだ。しかし、出生率の水準はまだ低い。
一方、2008年の日本人の平均寿命は男性が79・29歳、女性は86・05歳で、いずれも3年連続で過去最高を更新した。
このようななか、わが国は2005年から人口の減少傾向が続いており、他国に比べようがないほどのスピードで少子高齢化時代に突入している。このままいけば、2055年には現在の人口の約3割が減少すると見込まれている。
人口の減少は、わが国の経済社会に深刻な影響を及ぼす。また、医療・介護・年金などの社会保障制度においても現役世代の負担が増加し、制度の維持が困難となることは明白である。
いままでの社会保障制度では、どちらかといえば高齢者に重きを置いた政策が推進されてきた感が強い。しかし、わが国の将来を考えた場合、少子化や子育てに関する政策は、最も優先すべき課題である。
本年10月から国の少子化対策の一環として出産育児一時金等が4万円引き上げられ、原則42万円となる。本年1月から導入された産科医療補償制度による3万円の負担増を加えると、短期間で一挙に7万円も引き上げられることになり、健保財政はさらに苦しくなる。健保組合にも一部国から補助が出るとのことであるが、国の政策であるから、保険者を苦しめるのではなくすべて国が負担すべきである。
また一方では、子どもの誕生を望んでいるにもかかわらず、不妊治療費が高額なため、途中であきらめてしまう人も多い。不妊治療には年間で平均41万円もの費用がかかるといわれている。自治体等での費用補助もあると聞くが、国が少子化対策に本腰を入れるのであれば、この費用も本来は国が負担すべきである。
ある健保組合では保健事業として特定不妊治療をされている加入員に費用補助を行っているとのことである。各健保組合でも、少子化対策の一助となる独自の保健事業を検討してみてはどうであろうか。
ともあれ、新政権は、子ども手当や教育費用の無償化など対症療法的なバラマキではなく、待機児童をなくすための保育所の増設や女性が出産後も働き続けられるような子育て支援制度の拡充など、早急に抜本的な少子化対策を講じてもらいたい。
そして、その対策に必要な財源についても、国民に少子化対策の必要性を分かりやすく説明して、消費税を含めた負担への理解を求める取り組みが必要である。 |
| |
(K・M) |
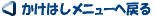 |
 |
|
 |