| |
|
| ●安心な医療保険制度・介護保険制度はどこへ |
| |
現在の被用者保険には、健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合等があり、被保険者と事業主がそれぞれ保険料を負担し保険給付はじめ諸事業が実施されている。しかし、全国健康保険協会には、すでに、給付費等の13%が国庫補助されており、制度として真に自立しているといえるかどうか…難しい状況にある。
一方、健康保険組合に加入しているわれわれは、現役を退いたら国民健康保険に加入することになり、退職者医療制度、前期高齢者医療制度、後期高齢者医療制度と経ていくことになる。 
このようなライフサイクルのなかにあって、健康保険組合に加入する、われわれ現役組合員は、各企業において一生懸命働き、収入にみあった「税金」を納め、加えて、健康保険料や介護保険料を負担することで皆保険制度の維持はもとより、社会の発展におおいに貢献しているといえる。しかし、時の流れとともに、誰もが、年を重ねていき、いつまでも健康であり、長寿でありたいという願いとは別に、いずれ医療・介護の世話になり、終末期を迎えることになる。
こうしたことを考えると、本年4月からスタートした「後期高齢者医療制度」、国庫補助のない「前期高齢者医療制度」、さらには、発足当初とは異なり、「在宅介護」が推奨され、「老老介護」世帯が急増する「介護保険制度」を取り巻く環境等は、75歳以上の人口が1300万人、70歳以上の人口が2000万人を超えるという、超少子高齢化社会とどう対峙させたらよいのか……不安と心配は尽きない。
現在もさることながら、今後、将来に向けて、安心して「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」ことができるのか……?。
いやいや「勤労の権利を有し、義務を負う」「法の定めるところにより、納税の義務を負う」を怠ってきたのか・・ますます心配は尽きない。
(第1地区 心配症) |
| |
|
| ●どうなる健保組合!? |
| |
ニュースや新聞紙上等で大きく報道されていた大手企業の西濃運輸健保組合に引き続き、京樽健保組合も解散に追い込まれた報道があった。
また、中国地方にある39の健保組合のうち、4組合が解散を検討していると中国新聞に掲載されていた。
原因は、西濃運輸健保組合と同様であり、新たな高齢者医療制度による負担増が組合財政を直撃していることが、さらに浮かび上がる状況となっている。
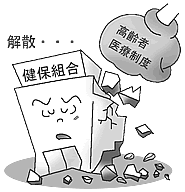 今後、新たな高齢者医療制度の負担金が増額すると考えると、大きく健保財政に影響を及ぼすこととなり「保険料率の引き上げ対応」か、極論は「解散」かの選択を迫られる健保組合が続出する可能性が高まってくる。 今後、新たな高齢者医療制度の負担金が増額すると考えると、大きく健保財政に影響を及ぼすこととなり「保険料率の引き上げ対応」か、極論は「解散」かの選択を迫られる健保組合が続出する可能性が高まってくる。
そうなれば、財政基盤に余裕があり、料率引き上げを我慢できる一部の大企業の健保組合だけが残るのではないかとの見方も広がっているのが現実なのではないだろうか。
当組合としても例外ではない。新たな高齢者医療制度による負担増により、今後、保険料率の引き上げを余儀なくされ、母体企業や被保険者の負担が増えることとなり、付加給付を廃止し、保養所運営を縮小したいま、健保組合としての存続意義がなくなってしまうこととなる。
さらに、高齢者医療制度の負担金と保険給付費の支出だけで赤字となってしまう状況となれば、保健事業に費用があてられない事態となり、これではなんのための健保組合なのかと思ってしまう。
(第2地区 M・A)
|
| |
| ●国民を惑わす厚労相の発言 |
| |
先日テレビで舛添厚生労働大臣が記者団に囲まれ、高齢者医療制度に関するインタビューを受けているなかで、ある質問に対して「潤沢な資金を持つ組合健保に多くの負担を課すのは当然」といったコメントを発していた。まるで組合健保には「お金の湧き出る泉」でもあるかのごとく。
多くの健保組合およびその母体企業が血のにじむような努力をして財政の健全化を達成してきたのに、そういった事実を全く無視したこのデリカシーのない発言に、私は心の底から怒りを覚えた。厚労相としてあまりにも安易すぎる発言だからだ。
一方では財政難に陥り解散する健保組合も新聞等で報道されており、厚労相の先の発言を聞いた国民のなかには、どちらの状況が真実なのか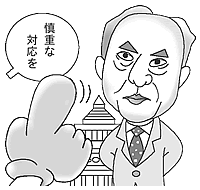 混乱している人も少なからずいると思う。 混乱している人も少なからずいると思う。
また、つい最近(9月下旬)も「後期高齢者医療制度に代わる新しい制度」の検討を表明しており、これについても一貫した主義主張のない日和見的な厚労相の姿が浮かび上がる。
私としては舛添大臣に期待するところが大きかっただけに、この一連の姿勢は残念でたまらない。高齢者の不満を最優先して、本来の制度改革の目的・理念まで見失うことのなきよう、今後の厚労相の慎重な対応を切に願う。
(第3地区 K・K)
|
| |
|
投稿規定
|
|
「言わしてんか!聞いてんか!」
|
| ■ |
500字以内。手書き、ワープロ自由。見出しも付けてください。原稿を添削する場合があります。 |
| ■ |
イラスト、写真も歓迎します。 |
| ■ |
原則として、投稿者の「所属組合名と実名」を掲載。匿名希望(イニシャル)の場合も、原稿には「所属組合名と実名」を明記してください。 |
| ■ |
原稿は地区会の広報委員へ送ってください。 |
| ■ |
問い合わせは、健保連事務局・辰巳(06-4795-5522)へ。 |
|
|
|
| |
|
|