| |
|
| ●格差考 |
| |
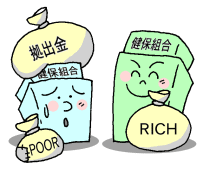
民主主義、資本主義の世界においては、活性化をはかるため競争の原理を働かせることは容認せざるを得ないが、これが行き過ぎると、強者・弱者の差が大きくなり、社会的な問題となる。
健保組合も、母体企業等の業績により、賞与、標準報酬等に差が出て、保険料率もさまざまとなって、健保組合間の格差が大きくなってきている。この格差の拡大に拍車をかけたのが老人保健拠出金である。収入を無視した過大な負担に、業績の低迷している母体企業をもつ健保組合は四苦八苦してきた。
今度の医療制度改革、とくに高齢者医療制度はどうか。
支援金?納付金(調整金)?名前は変えたが中身の算出方法は拠出金と同じではないか。これでは、また格差が開いてしまう。緩和措置は考えられているようだが、根本がダメだ。
せめて被保険者が納得できるような方法、例えば、同一の保険料率での徴収、拠出は考えられないものか。
(第4地区 H・K) |
| |
|
| ●メニューはより取り見取り |
| |
2005年の概算医療費が発表され、対前年度比3.1%増の32兆4000億円と過去最高となったとのことである。
順調(?)に増加しているが、今回成立した医療制度改革法の前提にある今後(特に高齢化ピークといわれる2025年の医療費)の予測数字は、これほどご都合数字で計算されている数値はないとのことである。
もちろん前提となる諸条件は変わってきているのだろうが、1995年時の推計値では141兆円、97年時には104兆円、01年時には81兆円、直近では65兆円で今回の改革が論議されたと思いきや、いつのまにやら見込まれる数字が56兆円に変わり、これが改革で48兆円になるというのである。実に95年時の推計値の3分の1である。
さらに5月の「社会保障の在り方に関する懇談会」では25年の社会保障給付が72%増、国民負担率53%になるので、保険給付の内容・範囲の見直しについて一段の社会保障改革が必要であると結んでいる。
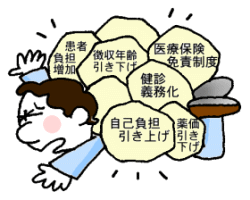 自己負担の引き上げ、患者負担の増加が実施され、そのあと給付費の引き下げに出るわ出るわ、健保組合への健診の義務化、医療保険の免責制度や包括(定額)制、介護保険の自己負担引き上げ、徴収年齢の引き下げ(?引き上げ)、社会保障番号の導入、総額医療費の管理、薬価の再引き下げ、パートの保険加入拡大がメニューにあがったかと思えば、いつのまにか社会保障費の歳出削減が国の財政健全化政策に組み込まれ、税制まで巻き込んで消費税の値上げやインボイス(明細書)制度までなにもかもみんな社会保障費が諸悪の根源の様相を呈してきた。 自己負担の引き上げ、患者負担の増加が実施され、そのあと給付費の引き下げに出るわ出るわ、健保組合への健診の義務化、医療保険の免責制度や包括(定額)制、介護保険の自己負担引き上げ、徴収年齢の引き下げ(?引き上げ)、社会保障番号の導入、総額医療費の管理、薬価の再引き下げ、パートの保険加入拡大がメニューにあがったかと思えば、いつのまにか社会保障費の歳出削減が国の財政健全化政策に組み込まれ、税制まで巻き込んで消費税の値上げやインボイス(明細書)制度までなにもかもみんな社会保障費が諸悪の根源の様相を呈してきた。
とにかく社会保障費憎けりゃ好きなようにやってください。
(第5地区 H・O) |
| |
| ●ウエスト基準は何㎝? |
| |
メタボリズム(代謝)とシンドローム(症候群)からできたメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)という言葉が大流行である。
20歳以上の有病者1300万人、予備群1400万人(2004国民健康・栄養調査結果:平成18年5月8日厚労省発表)と推計されるこの「内臓脂肪症候群」について、従来の健診から今後は内臓脂肪症候群予備群の早期発見を最優先とし、保険者に対し40歳以上の効果的・効率的な健診と保健指導を義務付け、実施目標が達成されない場合には、後期高齢者医療制度に対する財政支援にかかるペナルティが課せられることとなった。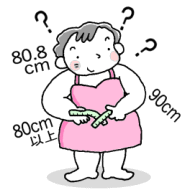
男性85㎝以上・女性90㎝以上が国内の診断基準とされていることはご存知のとおりだが、最近の研究によりこれ以外の数値等についても発表されている。
欧米諸国では、内臓脂肪症候群の概念は一般的ではないといわれているが、それは別としても日本の基準値に差があっては混乱の元となるのではないか。
「女性は80㎝以上と厳しくすべきで、男性はもっと基準を緩めるべき」、との研究結果では、女性80㎝を境に心筋梗塞などの発症リスクが1.6倍に高まり、現在の基準の90㎝では発症リスクに変化はない。また、男性83.7㎝、女性80.8㎝で血圧などの数値が2つ以上高い人の割合が急増したと発表されているし、他の研究では「男性は90㎝を境に心血管病の発症リスクが高くなる」、等の結果が発表されている。
今春、厚生労働省が、健診24項目のうち有効なのは9項目のみであったと発表したが、「健保は経費ばかりがかさみ、予防効果には疑問」との声も多いと聞く今日、新しい健診が効果的に実施できるように基準をしっかりと決めてもらいたいものである。
(第6地区 T・S)
|
| |
|
投稿規定
|
|
「言わしてんか!聞いてんか!」
|
| ■ |
500字以内。手書き、ワープロ自由。見出しも付けてください。原稿を添削する場合があります。 |
| ■ |
イラスト、写真も歓迎します。 |
| ■ |
原則として、投稿者の「所属組合名と実名」を掲載。匿名希望(イニシャル)の場合も、原稿には「所属組合名と実名」を明記してください。 |
| ■ |
原稿は地区会の広報委員へFAXで送ってください。 |
| ■ |
問い合わせは、健保連事務局・辰巳(06-4795-5522)へ。 |
|
|
|
| |
|
|