 |
 |
健保連の高齢者医療制度等ワーキンググループ(WG)は、昨年3月に閣議決定された「医療制度改革・基本方針」にそって、新たな高齢者医療制度の創設に向けた検討を行い「現時点の取りまとめ」を公表した。
次期医療制度改革に対する基本的な考え方と「基本方針」の問題点を改めて整理し、高齢者医療制度の創設で解決すべき事項や課題を提起している。
医療保険制度の基本的な考え方として、自助・共助に基づく社会保険方式の堅持と、被用者保険と地域保険の二本立ての制度体系とすることに置き、従来から健保連の主張する高齢者医療制度は一般の医療保険制度とは切り離し独立した制度として確立すべきことを指摘した。
とくに、年金や介護保険の給付年齢との整合性も考慮し、年金受給者に対する医療保障の観点から「原則として65歳以上」を対象とした制度とすべきとしている。
「基本方針」が盛りこんだ高齢者医療制度の考え方に対しては、現行の老人保健および退職者医療両拠出金制度の廃止を評価する一方、拠出金制度が持つ問題点が解決されていない。75歳の前後で、前期高齢者と後期高齢者に分けて制度設計するとしているが、前期と後期と全く違った制度および負担の仕組みとなっており、合理的でないと指摘している。また、高齢者医療費の抑制、現役世代の負担上限の設定を求めるとともに前期高齢者における保険料負担や公費負担の投入の必要性を強調した。
さらに、現行の高齢者医療制度では、運営主体が不明確で一方的に拠出金を賦課されることから新たな制度設計にあたっては、各医療保険者が制度の運営に直接参画できる仕組みを考えるべきとの方針も打ち出している。
この点について健保連では閣議決定された「基本方針」の重みは承知しつつも、社会保障審議会・医療保険部会の秋口からの審議の場においてこの考えをしっかりと主張・意見反映させ、的確に対応していただきたい。
こうした問題点をチェックしてみると、「基本方針」が閣議で決定されたからといって、絶対に動かすことのできないものとはいえないだろう。
高齢者医療制度のあり方について、制度を75歳で分けるという考え方も、その根拠を国民に分かりやすく的確な形で示すべきであり、保険者としても、負担について理解と納得ができる仕組みとし、「社会連帯的な保険料」を納めるのであるから、金も出すが口も出せるシステムを構築しなければならない。
全ての組合が英知を出し合い確固たる方針を早く決定、具体的な制度像を明らかにしてほしい。 |
|
(宏) |
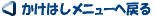 |
 |
|
 |