 |
 |
健保組合全国大会で「医療制度改革の前倒し実施」がスローガンとなっているのは健保組合全体が危機的状態にあるからである。平成20年度まで耐えられる体力はなく、特別の緊急対策が是非必要とされる。
今、平成16年度の健康保険組合予算の編成に腐心している。社会保険事業には保険料収入で保険給付等を賄うという原則があり、会計年度独立の原則もある。
「入るを量りて出ずるを為す」とは、収入の額を計算しそれによって支出を計画することである。「入るを量りて出ずるを制す」は個人の場合給与が減れば支出を制限することですむ。しかし健保組合の支出は制することはできないので、支出に必要な収入額を保険料率で調整することになるが、料率設定には制限もあれば、負担する側の事情もある。収入のほとんどは保険料である。総報酬制で多くの組合は保険料率を引き下げ、賞与分の収入を併せて計算し、財源を確保している。つまり賞与月の保険料収入額は他の月の2倍であったり3倍であったりもする。14年度までとは大きく異なり毎月ほぼ均等の収入でない。
一方支出の殆どが拠出金と診療報酬であることは占める割合こそ違え全組合の共通項である。
さて、拠出金の徴収については、社会保険診療報酬支払基金老人保健関係業務方法書に定めがある。総報酬制実施と時を同じくして、平成15年4月1日から方法書の一部が変更された。それまで「拠出金は各月に均等に分けて徴収する」が「平成15年度から平成18年度の拠出金の額のうち前期概算医療費拠出金は4月から10月までの各月に均等に分け、後期は11月から3月までの各月に均等に分けてそれぞれ徴収する」となったが均等に変わりはない。
業務方法書は支払基金が定め厚生労働大臣が認可して施行される。支払基金や厚労省が、被用者保険の財政状況や総報酬制導入を埒外に徴収や市町村に交付することの都合だけで定めたとすれば、納付側にとってあまりにも不都合だ。16年4月から診療報酬等にも延滞金が課せられる。収入の状況で拠出金と診療報酬のいずれか、または両方とも納入期日に納入できないことも当然おこる。
「入るを量りて出ずるを為す」には均等であってはこまるのである。徴収側の事情もあるのだろうが納付側の事情もある。一旦認可された業務方法書は変更できないのだろうか。
15年度第1期分納付時に均等拠出額について照会した。その時あった「貴重な申し出です。次回検討します」の答えが虚しい。16年度の拠出金も均等に分けた期別内訳と、納付書が送付されるそうだ。 |
| |
(充) |
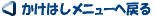 |
 |
|
 |