| |
|
| ●憂える |
| |
 ・保険財政に憂える ・保険財政に憂える
5年前に比べ積立金が約50%減った。本年度も繰入れる予定。翌年度はどうなる?憂える。
・総報酬制に憂える
健康保険法の一部改正で事業所に対して調査を行った。平成15年度には保険料率を引き下げる予定。マイナス成長の時代、賞与は支給される?維持できる?保険料率はどうなる?憂える。
・健康保険法改正に憂える
平成14年10月1日から健康保険法が改正されたがその中でも特に高額療養費の取り扱いがわかりにくい。上位所得者、一般、市区町村民税非課税世帯、70歳未満の者、高齢受給者、世帯合算etc。提出してもらうもの、計算等、憂える。
・パートの健保加入拡大(厚生労働省検討)に憂える
ある新聞でみた。厚生労働省はパートタイム従業員の健康保険加入を増やす方針と書いてあった。「保険料収入を増やし、悪化した医療保険財政を安定化するのが狙い。」とのこと。確かに加入者は増える。だが、報酬月額は?平均年齢は?悪化した医療保険財政の安定化につながる?憂える。
顧みれば、健康保険組合の仕事を担当する様になってから心の休まることがあっただろうか?保険財政のこと、老人保健制度、退職者医療制度、健康保険制度の幾度かの改正。その度、健康保険組合の運営が大変になるように思う。企業でも同じように赤字が続けば、経営は大変だろうが、母体企業と健康保険組合の運営に乖離を感じ、憂える。
健全で憂いのない未来のある健康保険組合の運営を夢みて、今後の高齢者医療制度の創設等、医療制度抜本改革に期待する。
(第1地区 Y・Y) |
| |
|
| ●廃止された、205円ルールの実態 |
| |
小さな話題で恐縮だが、医療保険で不合理な慣行がいくつかある。
その一つで205円ルールと呼ばれる薬価請求の方法が4月から廃止された。今回の改定で、機械処理のレセプトは投与した薬剤名等を記載し、届け出を行った手書きのレセプトでは175円を超えたときは薬剤名を記載することとなった。手書きレセプトの記載に不満が残るものの、不合理、不透明な部分がやや解消された。
旧ルールでは、医療機関がレセプトを作成する際、薬剤1剤あたりの請求額が205円(20点)までは薬剤名・投与量を記入する必要がなかったので、実勢以上の価格で請求しても保険者はチェックの方法がなかった。極論だが、従来では1日あたり10円の薬剤を投与しても、200円の収入を得ることも可能であった。仮に慢性疾患で30日分の投与を受ければ保険者は不当な請求により1カ月あたり5、700円の支出増となる。しかも205円ルールに基づく請求が年々増加しており、統計ではその請求比率が50%を大幅に超えているとのことで、これが実際以上に医療費を押し上げているのではないかと思われる。
さて、当組合では改定前後のレセプトを時系列で検証?した。はたして旧ルールによる不当な請求があるのか興味があった。主として慢性疾患で治療中の被保険者で、継続して治療中のもの40人を抽出した。やはり不透明なレセプトはあった。
改定後4月診療分の請求では、投与した薬剤名、使用量を明記するため同じ薬剤の投与を受けたと思われる3月分に比べかなり低い点数で請求されていた。3月分までは長期に亘り明らかに不当な請求が行われていたことになる。
 具体例では、改定前は1日当たり190円と200円の2剤を投与されていたものが4月分では同じ薬剤の投与を受けながらそれぞれ120円、110円の請求となっていた。薬剤名・使用量を記入するため不当な請求ができなくなったものと思われる。前述のような事例は当組合だけでも10件以上確認され、特に手書きレセプトに多く見られる結果となった。 具体例では、改定前は1日当たり190円と200円の2剤を投与されていたものが4月分では同じ薬剤の投与を受けながらそれぞれ120円、110円の請求となっていた。薬剤名・使用量を記入するため不当な請求ができなくなったものと思われる。前述のような事例は当組合だけでも10件以上確認され、特に手書きレセプトに多く見られる結果となった。
レセプトのコンピュータ処理が進む中、205円というルールに守られて不当な請求方法がまかり通ってきた。このルールがもっと早く廃止されていたらと思う次第である。
(第2地区 I・K)
|
| |
| ●ペイオフ解禁を控えての雑感 |
| |
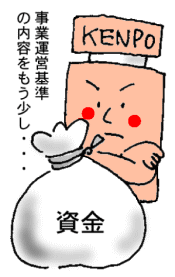 従来、行政から一挙手一投足に至るまで、規制を受けてきた健保組合が、規制緩和の方向にあるなか、組合の事業運営基準改正がなされようとしている。 従来、行政から一挙手一投足に至るまで、規制を受けてきた健保組合が、規制緩和の方向にあるなか、組合の事業運営基準改正がなされようとしている。
しかし、資金運用管理について、従来の基準が不十分ということで、逆に規制が強まる方向にあると推察される。
エンロン債を組み込んだ投資信託、アルゼンチン債のデフォルト等の社会問題が背景にあり、資金運用での自己責任の原則の適用は何とかならないかとは思うが、公益性の高い健保組合といえども、例外なく適用される。
私どもの組合でも昨年度末、ペイオフ一部解禁に備え、雀の涙ほどの準備金の扱いをどうするか議論した結果、一部を、定期預金から短・中期の国債等の購入へ充てるなど資金運用先の変更を行い、万が一の事態にも、組合員へは説明出来るように備えたが、その際、改めて知ったのが、世の中の流れに追いついていない事業運営基準の内容である。
運営基準‥「準備金の保有方法について」では、銀行等の金融機関への預金がベストであり、最も安全とされる国債(日本)・地方債等の保有でも、保有量は準備金総額の2分の1を超えてはならないとしているほか、運用先を非常に具体的に示している。資金運用担当者からすれば、「余計なお世話」といいたいところである。
金融機関の破綻があいつぐなかで、こういう時代錯誤?の基準は、いうまでもなく、すみやかに改めて欲しいと思うばかりである。
しかし、行政基準というものは、一度定められると余程のことがない限り、すぐには変わらないことが多い。
従って、とりわけ激動期の中にある金融情勢下だけに、こういう基準(規則)改訂の場合、あくまで自己責任を前提に、がんじがらめ・規制一辺倒で融通が利きにくい、あまり細かい基準にならないようにしていただけないものであろうか。
(第3地区 M・F) |
| |
|
投稿規定
|
|
「言わしてんか!聞いてんか!」
|
| ■ |
500字以内。手書き、ワープロ自由。見出しも付けてください。原稿を添削する場合があります。 |
| ■ |
イラスト、写真も歓迎します。 |
| ■ |
原則として、投稿者の「所属組合名と実名」を掲載。匿名希望(イニシャル)の場合も、原稿には「所属組合名と実名」を明記してください。 |
| ■ |
原稿は地区会の広報委員へFAXで送ってください。 |
| ■ |
問い合わせは、健保連事務局・辰巳(06-4795-5522)へ。 |
|
|
|
| |
|
|