 |
 |
| ●国民年金 第3号被保険者と健保組合 |
| |
国民年金第3号被保険者制度は、昭和60年の公的年金制度改正で創設された。この制度は第2号被保険者の被扶養配偶者(一般的にはサラリーマンの妻)を対象としたものであり、当時はサラリーマンへの年金給付から、妻の基礎年金を分離することとなって「婦人の年金権が確立された」と評価されたものである。
しかし今やこの制度は、女性の社会進出の増加等社会情勢の変化に伴い多様な見解が示されている。サラリーマン世帯の専業主婦が基礎年金の保険料を負担しないのは、働く女性と比べて不公平だとするのも制度に対する批判的な意見の一つでもある。
夫に依存する第3号被保険者は自分の意思にかかわりなく、夫の職業の変遷に伴って年金上の地位も決定される。しかしながら本人が保険料を納めることを要しないことから、国民年金への加入意識が希薄で、その結果届出漏れが生じ、年金額が減額されたり、年金給付に結びつかなくなることもあったそうだ。つまり年金の加入期間に空白が生ずるということになる。これらの防止を目的に健保組合は健康保険の被扶養配偶者認定時に「国民年金第3号被扶養者届出周知シール」を貼りつける協力を行っている。
さて、第3号被保険者の届出は本人が市町村に届けることとされていたが、平成14年4月からは、配偶者である第2号被保険者の事業主を経由して社会保険事務所に届け出ることになる。改正後の国民年金保険法第12条第8項によれば「事務の一部を当該事業主等が設立する健康保険組合に委託することができる」となっている。
届出忘れのために年金の加入期間に空白が生ずることを防止するために、事業主や健康保険組合が届出をすることに協力は惜しまないが、責任は重大である。
例えば健保被保険者の老齢基礎年金の受給権や年齢、被扶養者の年齢などで第2号や第3号の被保険者であったりなかったりと、国民年金制度について十分な知識がなければおいそれと引き受けられる代物ではなさそうだ。
平成14年の予算説明会で、事業主から事務委託を受けた場合、委託費を計上してもよいとの話であったが、適正な費用とはいかほどになるのやら、費用徴収は実行することができるのか。
政管健保の届出様式は示されるとのことだが、組合健保の場合この様式は独自で作製することになるのだろうか。事業主や組合が重大な責任を負うことになるうえに、様式等の作製が各組合でとなると、事務手数が増えるだけでなく、経費の負担増にもなる。健保の被扶養配偶者のためにではなく、第3号被保険者のために。健保連が様式を作製して配付していただければ、随分助かるのだが……有償であってもである。
4月からの実施となると残された時間は少ない。早く具体的な取り扱いが示されるのを待ち望んでいる。 |
| |
(充) |
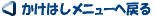 |
 |
|
 |