 |
|
|
| ■2001年8月 No.359 |
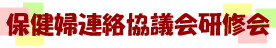 |
| |
さる7月11日、保健婦連絡協議会の研修会が大阪厚生年金会館で実施された。今回の講師は、「専門のお医者さんが語るQ&A 骨粗しょう症」の著書もある、辻学園栄養専門学校の広田孝子教授。「元気で長生きするための食事学」と題して講演しました。 |
| |
※写真をクリックすると拡大写真がご覧になれます。 |
| |
人の健康状態は、必ずしも暦年齢と肉体的年齢が一致するものではありません。遺伝的因子だけでなく長年の生活習慣との関係も深いものです。
また、現在の食生活の実態はどうでしょうか。脂肪のとり方や糖分のとり方、高カロリー食の摂取については、各年代ごとに特性があります。特に、脂肪の摂取比率が、総カロリーの4分の1を超えてしまう人は食生活に問題があるといわなければなりません。
|
 |
| 広田 教授 |
|
| |
加齢による健康問題として性ホルモンの変化による骨粗しょう症や循環器系疾患の増加があげられます。予防医学的立場から重要なのが思春期の食生活です。
骨粗しょう症は女性ホルモンとの関係が深いが、これを予防するには、①カルシウムは1日800㎎以上、②栄養バランスのとれた食事、③適正体重の維持、の3ポイントが大切です。特に③については、過度の無謀なダイエットはしないことを心がけてください。
また、循環器系疾患については「死の四重奏」という言葉があります。これは①上半身肥満、②高コレステロール、③高血糖、④高血圧の4つです。コレステロールを下げるにはカロリーオーバーにならないこと、食物繊維や大豆蛋白、魚介類をたくさんとることをお勧めします。 |
| |
|
| ●長生きする条件は |
| |
そのほか、最新の栄養学情報としてお伝えしたいのは、老化防止には抗酸化物質、動脈硬化予防にはビタミンB6、B12、葉酸が効果的です。また、イソフラボンには女性ホルモン作用が期待できます。
なお、長生きの条件は①太り方は中くらい、②血中アルブミンや鉄が高いこと、③牛乳を飲む、④油料理は適量に、⑤お酒は少々、⑥禁煙、⑦スポーツをする、⑧握力が強いこと、⑨社会的活動をする、⑩記憶力がよい、といった点です。
これら「健康日本21」の指標を高めていくことが、病気を予防し、老化を遅らせることは長生きにつながります。 |
| がん予防のための食生活 |
世界がん研究基金、米国がん研究財団の調査より引用
| ① |
適正体重は18.5~25(BMI)維持。 若い頃の体重より+5キロ未満がよい。 |
| ② |
運動は速歩など1日60分、週に1時間は激しい運動を。 |
| ③ |
酒は勧められない。(酒は1合、ビール2杯以下) |
| ④ |
禁煙。 |
| ⑤ |
野菜、果物、豆類、精製度の低いでんぷんをとる。 |
| ⑥ |
野菜、果物は400~800g/日以上。 |
| ⑦ |
穀類、豆、芋、バナナは600~800g/日。 |
| ⑧ |
牛肉、羊肉、豚肉は80g/日以下。 |
| ⑨ |
動物性脂肪を控える。 |
| ⑩ |
塩分は6g/日以下。 |
| ⑪ |
カビ防止。 |
| ⑫ |
直火焼き、焦げは避ける。 |
| ⑬ |
健康食品は不要。 |
|
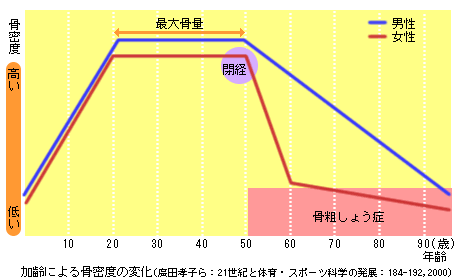
|
 |