 |
 |
新型コロナウイルス感染症の拡大は、実質GDP成長率1.4%を見込んでいた経済に、リーマンショックを超えるとされる大きなダメージを与えた。健保組合は保険料収入が減少し、財政は悪化した。さらに、標準報酬総額等の低迷が長期化する見通しである。2021年度は6700億円、2022年度は9400億円という衝撃的な赤字が想定されていることから、極めて深刻なお金の問題が生じてしまったということになる。
健保組合は事業運営に必要な保険料収入が不足すれば赤字になる。赤字が続けば解散の危機だ。存続や安定のためには、入るを量りて出ずるを制することの徹底が必要だが、各健保組合の個別の努力は、もはや限界に達している。
2019年10月の消費税率の引き上げで、社会保障と税の一体改革は一区切りとされた。一方で、拠出金負担は極めて重いままだ。財政赤字の健保組合は、なかなか将来を見通すことができない。
消費税率引き上げの直前に始まった全世代型社会保障検討会議では、健康保険制度のあるべき姿をまず議論すべきとの方針のもと、2019年12月に75歳以上の方の2割負担の方向性が示され、その基準が注目された。
その後、新型コロナウイルス感染症の拡大により、医療保険制度改革のとりまとめは本年末となった。然るべき結論を然るべき時期に得て、これを実施できるのかが危惧される。経済は、かつて目指していた2%の物価上昇とは懸け離れた状態にある。そして、2022年まであと1年あまりだ。
健保組合の赤字対策は、時間制限のあるお金の問題だ。体力がある間に対策の効果が現れなければ、解散に追い込まれてしまう。
人生100年時代。健康寿命の延伸は人生の充実につながる。特定保健指導や前期高齢者の重症化予防は、そのための重要な取り組みだ。ただ、医療費の削減効果という面では、極めて重い拠出金負担で悪化した健保組合の財政を短期間で改善できるわけではない。
ならば、保険料率を引き上げ、保険料収入を増やすことを検討する。しかし、保険料率を引き上げても赤字を解消できず、将来を見通すことができなければ、被保険者、事業主、労働組合の理解と納得を得ることは難しいだろう。
政府が2019年度から位置づけた2021年度までの「基盤強化期間」とは何だったのか。今重要なことは、限られた時間のなかで、制度改革に踏み込んだ実効ある対策の実現により、V字回復とはならない経済下において、存続の足掛かりを築くことだ。
このようななか、今年8月、自民党の有志議員による「国民皆保険を守る国会議員連盟」が発足した。設立趣意書には、高齢者医療費の負担構造改革が急務とある。とても心強い。
2021年は丑年。丑は、芽が種子のなかに生じてまだ伸びることができないさまだ。医療保険制度改革の中身は、健保組合の存続に直結する。我々は時間制限のあるお金の問題の解決のため、その芽を伸ばし、果実を手にしなければならない。 |
| |
(H・I) |
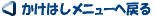 |
 |
|
 |