 |
ハラスメントの基礎知識とメンタルヘルスとの関連
― ハラスメント発生を防ぐポイント ― |
| 6月21日、大阪商工会議所で心の健康講座を開催。和歌山県立医科大学 医学部 衛生学教室 講師 津野 香奈美氏が「ハラスメントの基礎知識とメンタルヘルスとの関連―ハラスメント発生を防ぐポイント―」をテーマに講演されました。参加数は49組合・69人。(以下に講演要旨) |
 |
| |
 |
| |
津野 香奈美 氏 |
近年、職場における様々な「ハラスメント」が話題に上がっている。ハラスメントは大きく分けて「性や性別が関わるもの」と「性・性別が関わらないもの」があり、前者にはセクシュアル・ハラスメント(セクハラ)、ジェンダー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント(マタハラ)、後者にはパワーハラスメント(パワハラ)等が挙げられる。このうち、セクハラに関しては男女雇用機会均等法によって事業主に防止措置が義務付けられており、マタハラに関しても男女雇用機会均等法および育児・介護休業法によって違法行為とされ、さらに平成29年1月からは、事業主に防止措置が義務付けられた。
一方、ジェンダー・ハラスメント(いわゆる性役割の強要)については、女性労働者のみにお茶くみや掃除当番等をさせることが配置に係る女性差別とされているだけで(男女雇用機会均等法)、特に法律によって規定されていない。また、パワハラについても、厚生労働省から防止ガイドラインが出るにとどまっている。
このようななか、ハラスメントに関する相談件数は増え続けている。厚労省の平成28年度個別労働紛争解決制度施行状況によると、労働者から寄せられた個別労働紛争に関する相談で最も多いものが「いじめ・嫌がらせ」であり、全体の22.8%を占めている。その10年前の平成18年は8.9%であったことから、いかに急増しているかが分かる。また、精神障害・自殺に関する労働災害の認定件数のなかでも、最も多い内容が「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」(平成28年の認定件数74件)であり、こちらも増加傾向にある。
では、日本全国ではどのくらいの労働者がハラスメントにあっているのだろうか。筆者らが全国から二段階無作為抽出した男女5000名を対象に行った調査では、日本人労働者の6%が「過去30日の間に職場でいじめにあった(セクハラ、パワハラ含む)」と回答した。日本の雇用者数が約6000万人であることを考えると、その6%は360万人である。これは都道府県別人口で、第10位に位置する静岡県とほぼ同じ人口であることを考えると、かなりの被害者の数だといえるだろう。
ハラスメントがもたらす健康影響は多岐にわたる。研究においては、抑うつ症状やうつ病はもちろん、心的外傷後ストレス障害、虚血性心疾患、線維筋痛症を発症させることが報告されている。また、ほかの職場のストレス要因にはない特徴として、ハラスメントを直接受けていなかったとしても、その様子を目撃した労働者がメンタルヘルス不調になることも明らかになっている。この理由として、目の前でハラスメント行為を見た際に、次に自分が標的にされるのではないかと恐怖を感じること、そういった行為を止めることのできない無力感を感じること、また、部署全体の士気や生産性低下等により心身の負担が増えること等が挙げられる。そのため、ハラスメントは起きてから対処すればよいというわけではなく、いかに発生そのものを防止していくか、または事態が深刻化することをいかに抑えるかが大事なのである。
ハラスメント発生には、組織の文化や職場の風土が密接に関わっている。例えば、人員削減・吸収合併等の大きな変化があった職場、上司のマネジメントスタイルが専制君主的あるいは放任的である職場、上司含め職員のストレス度が高い職場、正義感・使命感の高い職種(医療職、教職、警察・自衛官・消防職)が集まる職場ではパワハラが多く発生し、一方でセクハラを容認する風土がある職場、管理職に女性が少ない職場ではセクハラの発生が多いことが、研究で明らかになっている。そのため、ハラスメント防止には、職場風土がハラスメントを生み出したり、許してしまったりしていないかにまず着目する必要がある。組織も個人も、決してハラスメントを許してはならないという基本的態度に立ち返ることが、ハラスメント防止を進めるための重要な一歩であるといえるだろう。 |
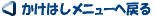 |
 |
|
 |