 |
| 健保連大阪連合会は4月16日、大阪市北区のホテルモントレ大阪で「2025年度の医療・医療保険制度改革を考える会」を開いた。会には約260人の健保組合関係者などが出席。近畿地区各府県からも多数の参加があった。会の前半に「これからの高齢者医療制度と負担の公平」をテーマに、土居丈朗教授(慶應義塾大学経済学部)が基調講演。後半には「2025年度の国民医療費の推計と健保連の主張」をテーマに、松本展哉企画部長(健保連本部)による勉強会が行われた。 |
 |
 |
| 小笹会長 |
会には、大阪府内の健保組合役職員などをはじめ、近畿地区各府県の健保組合からも多数参加があり、約260人が集まった。
大阪連合会・小笹定典会長は開会のあいさつで、「現役世代に課せられた高齢者医療への拠出金による負担にも限界がある。その負担を軽減するために、国民全体で負担の公平を図ることの必要性を訴えていきたい」と述べた。そして土居丈朗教授(慶應義塾大学)が
 |
| 牧野監事 |
「これからの高齢者医療制度と負担の公平」をテーマに講演。続いて、健保連本部の松本展哉企画部長が「2025年度の国民医療費の推計と健保連の主張」をテーマに、これから目指す医療保険制度改革への考え方について説明した。そして結びは、健保連の牧野純二監事のあいさつで締められた。
「受益と負担の世代間格差を是正」
土居教授
土居教授は、現状の医療制度における受益と負担の世代間格差や、これからも国民皆保険制度を維持していくための制度改正について、グラフ等を用いて分かりやすく説明した。
同教授は、現行の医療費の自己負担割合について「負担能力ではなく年齢に応じた負担である」とし、自己負担割合が低い高齢者の増加や、医療の高額化により、健保組合の保険財政が圧迫されていると指摘。そして、受益と負担の世代間格差が広がっていることについては、「現役世代の負担を抑えるための政策が求められ、現在の世代間格差を是正するためには、その財源として消費税を充当することが公平性の観点から適している」とした。
これらを踏まえ、人口の高齢化が進展するなかで、2019年度以降、新たに自己負担割合が1割となる後期高齢者については「引き続き、2割負担の対象年齢を引き上げていく必要がある」と述べた。制度の支え手が減少する反面、医療費は引き続き増大することが確実な状況で、現役世代の負担が限界に近づいていることについて、「負担の限界を意識し、現役世代・将来世代の負担が過重にならないよう、給付に歯止めをかける制度が必要」と説いた。
最後に同教授は、年齢ではなく負担能力に応じた負担を目指し、高齢者についても「原則自己負担3割とし、所得に応じて1〜2割の例外を設定する」という方向性を示した。
「国民皆保険制度を守るために」
松本企画部長
松本企画部長は、今まで健保連が主張してきた内容が、うまく改革に結びつかなかった点を踏まえ、これからの対応について説明した。
同部長は、「2025年度に向けた推計を健保連自身で行い、それを元にどのような改革が必要なのかを議論し始めた」と述べた。推計の結果は、新聞などのメディアでも取り上げられ、そういったなかで、昨年の9月に健保連は記者会見を行った。そして、国民皆保険制度を守るためには、抜本的な改革を断行すべきであり、「国も責務を果たし、国民の心構えも必要、
 |
| 石田常務理事 質問 |
そして保険者としても務めを果たさなければならない」と説いた。
また、最近では健保組合の解散事案が報じられており、やはり拠出金負担が最大の要因である。同部長は「協会けんぽの保険料率10%が数年先まで動かないといった状況で、すでに10%を超えている健保組合においては、運営が困難になってきている」と示唆した。
最後に、「これら健保組合を取り巻く状況を改善するための改革が手遅れになる前に、早急に対応すべく、健保連はこれからも活動を続けていくため、皆さんのご意見を伺いながら進めていく」とまとめた。
会場から2氏が質問・意見
土居教授、松本企画部長に対して、会場の2氏から質問や意見があった。
 |
| 土居教授 |
大阪鉄商健保組合の石田正雄常務理事は、高齢者医療制度への拠出金の増加や高額な医薬品などにより、財政運営が極端に困難な組合の状況を説明。「社会保障費には多額の公費が投入されている。しかし、高齢化や人口減少に伴う支え手の減少により、高齢者医療の負担構造改革や、踏み込んだ医療費適正化に取り組まない限り、国民皆保険制度は維持できないと考える。本年度における社会保障費抑制案について、地域別診療報酬や保険給付の範囲等について議論されていると聞いているが、今後の議論に対する土居先生のお考えをお聞かせ願いたい」と訴えた。
 |
| 朝倉常務理事 質問 |
これに対し土居教授は、財政制度等審議会委員という立場を踏まえ「消費税率を10%以上に上げるということは議論されていないが、2025年度を見据えると、今後考えられないことはない。現状、財源は兆円単位で不足しているにもかかわらず、数百億、数十億という抑制策に収まっていることには忸怩たる思いである。踏みこんだ議論をする時期に入っているという声を、皆さんから発していただけると、私も一緒に頑張りたいと思っている。また、地域別診療報酬制度について私は賛成だが、今はまだ効果が発揮できる状況には至っていないと思われる。ようやく国民健康保険が都道府県単位化されたが、いまだに法定外繰り入れが許されているようなところもある。税金を赤字の補填に回したり、保険料率の上昇を抑えたりするなどは控えるような議論から始め、なぜ保険料率がその基準になっているのか、給付との関係性を明らかにするべきである。健保組合は、税金による補助を受けずにやりくりしている。国保に対しても、給付の抑制など、真剣に取り組むための問題提起は非常に重要であると考える」と答えた。
 |
| 松本部長 |
続いてヤンマー健保組合の朝倉孝則常務理事は、松本企画部長に対し、高齢者医療費の問題や2025年度の医療保険制度について、「健保連は、昨年9月にマスコミに説明したり、国会議員に対してシンポジウムで訴えたりしているが、なかなか広く一般に広がっていないのではと思っている。健保組合としても取り組まなければならないが、今後、健保連で検討している取り組みがあれば紹介してほしい。また、医療費適正化について、社会保障費の伸びを3年間で1.5兆円に抑えるとあるが、年間5000億円という前提で動いてよいのかと思っている。例えば薬剤費を抑え、医療費などの問題を先送りにしたなかで5000億円以内に抑えたとしても、本当に効果的な対策に結びついているのか分からない。これらについてご意見があればお願いしたい」とした。
これに対し松本企画部長は、「国会議員に対しては各政党にお願いし、直接話を聞いていただく場を設けている。健保連の主張を理解していただき、国会で議論していただくことが最大の狙いである。そして今年6月には、経済財政諮問会議の骨太方針がまとめられるため、その改革工程表に健保連の活動を通じて改革項目に反映できればと思っている。また、社会保障費の抑制については、本年度の診療報酬改定で、薬価を大きく下げた分を本体部分に回したが、トータルはマイナス改定としたり、介護納付金の総報酬割による財源を充てたりするなど、健保組合の痛みを前提にした抑制策となった。今後は、健保組合の負担を増やし国費を浮かすなどというおかしな制度改正が行われないよう、医療費適正化や給付費抑制など、積極的な議論を進めていきたい」と答えた。 |
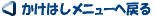 |
 |
|
 |