| ●恐るべし腸内細菌 |
| |
先頃、新聞で「人工甘味料で血糖値レベル上昇?」という記事を見つけました。読んでみると、サッカリンやアスパルテームといった人工甘味料は、消化されずに胃を通過して腸に達する。そして、腸内細菌の構成に変化を与えて耐糖能異常を引き起こし、糖尿病になる可能性があるというものでした。
なんということでしょう。糖尿病のリスクという点では、ダイエット炭酸飲料等と同種の他のドリンクに大した違いはないというのです。
私は以前に糖尿病と診断され、食事と運動療法を行った苦い経験があります。現在もカロリーを気にして、炭酸飲料等は人工甘味料が使用されたカロリーゼロのものを飲むようにしています。
それなのに、糖尿病を気にして飲んでいる飲み物が、逆に糖尿病を引き起こすとは本末転倒ではありませんか。
やはり化学に頼らず、摂取したカロリー分はちゃんと運動をして消費しなさいということでしょうか。健康に近道はないようです。
最近いろいろな病気でよく耳にする腸内細菌が、糖尿病でも関係しているとは思いもしなかった。人間の健康はひょっとしたら腸内細菌に支配されているのでは…。
(第1地区 T・T) |
| |
|
| ●右手が動かない?! |
| |
健保組合に異動する前の今年3月、いつもどおり出社の準備をしていたときのこと。シャツのボタンを留めようとしたが、右手の指が動かせない。
寝ぼけているのか。もう一度やってみよう。あれ、やっぱり動かない。どうしたのか。今日は大事な会議があるというのに…。
動く左手で着替えを終えて、なんとか出社。あわただしい1日を過ごし、やっと一息ついた夕方、保健室を訪れた。「右手の指が動かないんです」。「明日、病院に行ってください」と看護師。「明日から2日間出張です」。あ然とされた。
出張から帰った翌日、病院で医師の診察を受けた。「大丈夫ですか」。「まず脳梗塞が疑われます」。「え〜、脳梗塞ですか」。予想もしない診たてに絶句する。
「MRIを撮りましょう」。「ひと月前の脳ドックで、異常はありませんでした」。「なにをいってるんですか。いま、異常が出たから検査するんです」。ぴしりと諭された。
幸いにも脳梗塞ではなく、神経の圧迫が原因で、自然に回復するとの診断。だが、健康に対する意識の低さを大いに反省した。
私が2、3日休んだところで会社はつぶれまい。仕事よりは体が大事――といまは思う。忙しいときほど体を大切にしたいものだ。
(第2地区 A・M) |
| |
| ●継続は力なり |
| |
先般、とある柔整問題に関する研修会に参加しました。内容は、健保組合、後期広域連合、国保などさまざまな団体の取り組みが6つの事例として発表があり、盛りだくさんでした。久しぶりに眠気がおそってこない有意義な研修会でした。
柔整師の実態に触れると、保険者としては、どうしても「イタチごっこ」への「無力感」におそわれがちになります。けれども、今回の事例発表のなかで共通していえることは、柔整師側への直接的な対応もさることながら、受診者側への働きかけを継続していくことの重要さでした。
本当に効果があるのは、実は、頻回受診者へアプローチしてみることや、健保メディアを通じて適正受診の教育・啓発をしていくこと、あるいは、受診者へのアンケート回収を徹底するための督促に注力することにあると再確認しました。
一見地味ではありますが、信念を持って粘り強くやり続けることが、医療費適正化につながっていくのだということがよくわかりました。まさに「継続は力なり」です。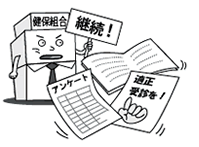
健保財政が厳しく、コストをかけて新しい対策を始めることが困難な環境ですが、今回勉強させていただいた内容を参考に、現在実施している「受診者側への取り組み」を粛々と実行していけば道は開けるという「勇気」をもらった気がします。
ここからは、余談ですが、この「柔整問題」をはじめ、「傷病手当金の継続給付」や最近よく話題に上る「海外療養費」などの問題は、きちんと法・制度の整備をして、ルールを強化することが急務なのでは?と思うのは私だけでしょうか。
政治家は、学者や大票田の顔色をうかがうばかりではなく、保険者の意見にも耳を傾けてもらいたいものです。
(第3地区 T・S)
|
| |
|
投稿規定
|
|
「言わしてんか!聞いてんか!」
|
| ■ |
500字以内。手書き、ワープロ自由。見出しも付けてください。原稿を添削する場合があります。 |
| ■ |
イラスト、写真も歓迎します。 |
| ■ |
原則として、投稿者の「所属組合名と実名」を掲載。匿名希望(イニシャル)の場合も、原稿には「所属組合名と実名」を明記してください。 |
| ■ |
原稿は地区会の広報委員へ送ってください。 |
| ■ |
問い合わせは、健保連大阪連合会事務局へ。(06-4795-5522) |
|
|
|
| |
|
|