 |

| |
あなたは普段、食品を買うときになにを参考に選んでいますか?栄養成分表示とは加工食品などの包装や添付文書に書かれている、その食品の栄養情報のことです。
表示をする場合は、エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・ナトリウムの含有量を必ずこの順番で表示することに健康増進法で定められています。含有量がゼロである栄養成分も、表示は省略されることはありません。つまり、その商品に都合のよい栄養素についてだけ選んで表示することはできないようになっています。また、この5つ以外の栄養成分は最後に記載されることになっています。 |
| |
この表示を参考に食品を選ぶ際に注意していただきたいことがあります。栄養成分表示として記載されている値は「100グラムあたり」なのか「1食分あたり」「1包装あたり」「1粒あたり」なのか、商品によってまちまちなのが現状です。このことから、複数の商品を比較する際などは単位に気をつけて数値を見る必要があります。
たとえば、「100ミリリットルあたり40キロカロリー」と表示されているジュースA1缶350ミリリットルと、「1缶350ミリリットルあたり96キロカロリー」と表示されているジュースB、すべて飲み干すとすると、どちらのほうがエネルギーが高いでしょうか? |
| |
次に、ナトリウムについてです。高血圧予防などを目的に塩分を控えていらっしゃる方も多いと思いますが「ナトリウム=食塩」ではありません。ナトリウムとは食塩を構成する成分の一部で、ナトリウムの値に係数2.54をかけると食塩相当量になります。
食事摂取基準では1日の食塩摂取目標量として、男性が9グラム未満、女性が7.5グラム未満を推奨しています。これをナトリウムに換算すると、男性ではナトリウム3543ミリグラム、女性では2953ミリグラムまでを1日あたりの目安と考えるとよいでしょう。 |
| |
「カロリーハーフ」「エネルギー2分の1」こんなキャッチコピーに惹かれて商品を手に取った経験はありませんか?こうした相対的な表示をする場合は、比較対象についても明示することになっています。たとえば「当社商品○○と比べてエネルギーが半分になります」といった表示が付け加えられています。また、「ハーフ」「微量」「△%」などの言葉・割合だけでの表示は許されていません。基本である5つの栄養成分の含有量についても必ず表示されていますので、参考にするとよいでしょう。
このように栄養成分表示の基礎を知っていれば、イメージにまどわされることなく上手に食品を選択することができます。ぜひ、あなたの健康づくりにお役立てください。 |
|
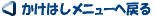 |
 |
|
 |